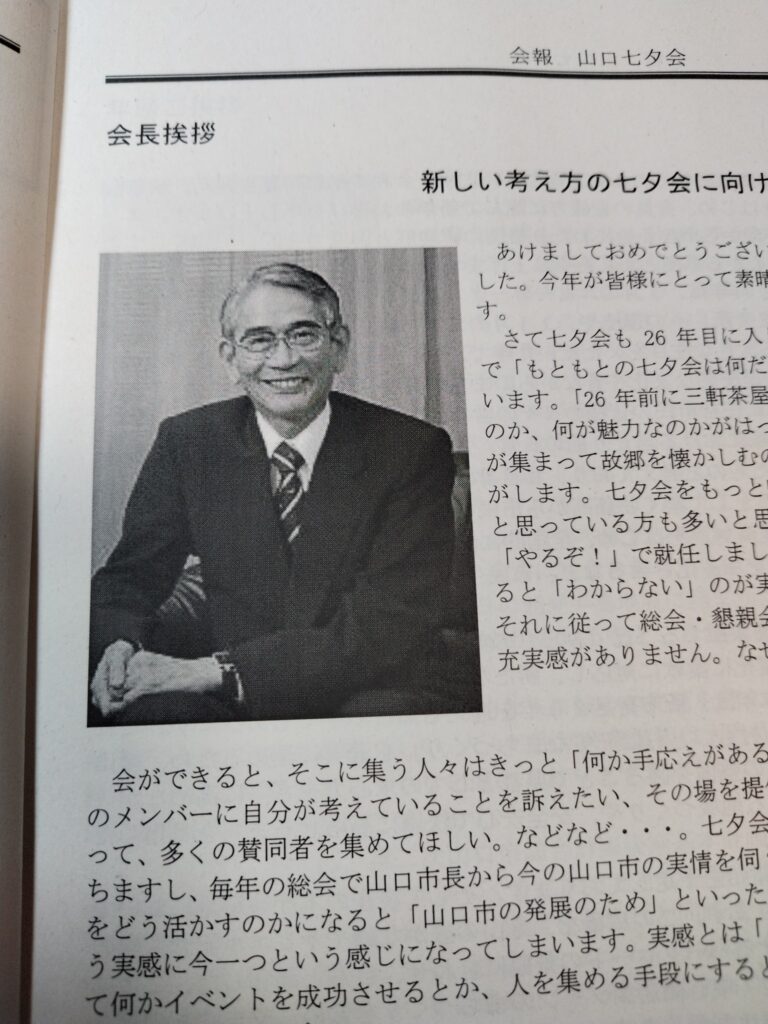山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2025年3月 トピックス】
◆マルクス経済花盛り
学生時代は学内でも「マル経」が大いに流行っていた感があった。
入学した当時、学園紛争はピークを過ぎていたが、一部では乱闘が残っており、入学したての頃は学内で授業ができなかった時もあった。
学校では学食にお世話になったが、恥ずかしながら授業にはあまり熱心に出たことはないが、先生方もマル経(寄り)の先生方が多かったように思う。
経済原論系では見野先生、若手の中尾先生がおられた。
このほかにも、上妻先生、小嶋先生、大林先生など。
鈴木先生もそうだったかもしれない。著作に「社会主義貿易論」というのもあったからだ。
◆マル経に対して「近経」は、福島先生、油の乗り切った安部先生、山本英太郎先生、若い吉村先生がおられた。
このころは、「近経」が徐々に市民権を得始めた頃だった。
しかし、よくよく見渡すと、経済史を教えておられた秋草先生、銀行論の安田先生、金融論の貞木先生、また、若手では名畑先生が途上国経済論を教えておられた。
秋草先生は白髪頭の老博士然としておられた。秋草先生の指定図書、先生が書かれた経済史の本は購入したものの、ほとんど手つかずだった。今にしてみれば、読んでおけばよかったと思うが、もう遅いか。
秋草先生のご子息秋草史幸氏はメガバンク勤務。一度鳳陽会東京支部の総会で、はやりの「MMT(モダン・マネー・セオリー)」について講演していただいた。また、史幸さんは温厚なお人柄で、在京の山口市出身者が集う山口七夕会・東京の会長を務めておられる。
貞木先生は山大経済卒で神戸大でドクターを取られ、山大経済助教授、教授を務められ平成24年秋に叙勲を受けておられる。
「パティンキン、パティンキン」とよくおしゃっていた。ケインズの中心要素は価格の変化ではなく産出または所得の変化に収斂するという独創的なアイデアだったというのがパティンキンの主張のようだ。
貞木先生はおしゃれでストライプの高級スーツを着ておられたが、大変なヘビースモーカーでもあった。
◆しかし、高校を出たばかりの私にとって、近経よりもマルクスこそが、「大人の社会」の入り口を見せてくれ、刺激的で、新鮮であった。
何も知らない大学一年生。
マルクスは、経済学にとどまらず、大まかに世の中を読み解く一つの見方、すなわち歴史・思想・哲学の体系ワンセットを私に示してくれた。
これに比べると、近代経済学は精緻だ。
精緻なだけに、ミクロのこと、すなわち一個人のこと、一企業のことをチマチマしているという印象があり、大胆に歴史の秘密を教え、哲学を骨太に訴えかけマルクス経済学に比べ、あまり魅力を感じなかった。
その当時は、ある行動や選択の精緻な分析や研究は二の次、三の次で、「おぼこな」私は、何よりも「思想・哲学」を求めていた。
(学23期kz)