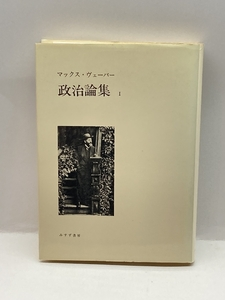山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2025年3月 トピックス】
◆「疎外」
マルクスも疎外という言葉をよく使っている。ドイツ哲学の流れだという。
当時は・・・からの自由、・・・からの逃避、・・・からの逃走、などというフレーズが流行し、その並びで・・・からの疎外という言葉も流行った。
マルクスは「疎外」に、編み出した唯物史観に沿って独特の深い意味を含ませた。
疎外・・・Entfremudung end(離れて)+ fremd(疎遠に)
自分が作った商品が自分を離れ、さらにはその商品が独立した力を持って作者に立ち向かう。
マルクスが使う「疎外」という言葉には、価値を生み出した「労働者」が重視されることなく、かえって資本の論理の下で人間性を否定されるというネガティブな響きがあった。
しかし大塚久雄先生の本で、マルクスは「疎外」というものを科学的な用語として使ったというくだりを見つけた。
情緒的・感情的な表現ではなく、経済なり歴史の「法則」、科学的な用語として使っていることを指摘したくだり。
「野球の試合が終わった途端、みんな一斉に出口から出ようとする。この時、出口の近くでは個人が自分の思う方向に身体を運びたくても、大きな強い流れに抗うことはできず、自分の意志とは無関係に出口から押し出される形になる」と。
なるほど。
妙に納得したことがもう一つあった。
資本論 Das Kapital・・・
定冠詞からわかるように資本(論)は中性名詞だ。
良いことにも使われ、また、とんでもない得体の知れない側面を持つ「資本」。
これが中性名詞・・・なるほどな。
◆ウェーバーと大塚久雄先生
ウェーバーの解説者となった感のある大塚史学の大塚久雄先生。
ウェーバーは資本主義の「精神」を解き明かした。
しかも宗教から。
キリスト教の中でも、カソリックではなく厳格なプロテスタントから解き明かしたことに意味がある。
両派はどう違うのか。
仏教、イスラム教でもそうだが、キリスト教でも労働、利子・利潤を得ることを、良しとしない。禁止している。
カソリックに比べ、プロテスタントは戒律に格段に厳しい。
しかし、このプロテスタントから資本主義の精神が生まれたとした。
何とも逆説的なストーリーではないか。
投機的な商行為で「暴利」を得ることは別として、隣人が真に必要とするものを生産し、商行為をなし、それによって、利潤を上げることは「隣人愛を実践する行為」すなわち自らの救済の手段となる。こうしたことは、むしろ「倫理的義務」であるとして、労働、利子・利潤を肯定した。
ちょっと待て。
日本でも似た話がある。商行為の倫理的意味付けは日本でも行われた。
しかもウェーバーが世に出る200年前に。
誰か 石田梅岩だ。
いやいや、さらにその100年前、すなわちウェーバーの300年前には鈴木正三がいたぞ。
両者については、稿を改める。
◆山大の中村貞二先生
ウェーバー研究といえば、山大経済にも中村貞二先生がおられた。
当時は中村先生に憧れた。
先生の著作は「みすず書房」から出ていた。
みすず書房は社会学系の分野に強い。
また、社会学といえば若い時代に水田洋先生が勉強されたように一橋大が強かった。
中村先生は山大経済を卒業され、一橋大の大学院社会学研究科博士課程へ。その後母校山大経済に戻り、助教授として教鞭をとられた。
もともとは神戸の生まれ、兵庫のご出身だ。
◆中村先生の講義を私が聴講したのは、先生が助教授時代だったのだろう。
当時、先生は頭髪にやや白髪の筋が見え始めたころだった。
物静かで禁欲的な風貌で潔癖そうなご性格に見受けられた。
先生はその後東京経済大学に移られ、同大学の名誉教授におなりになっている。
(学23期kz)