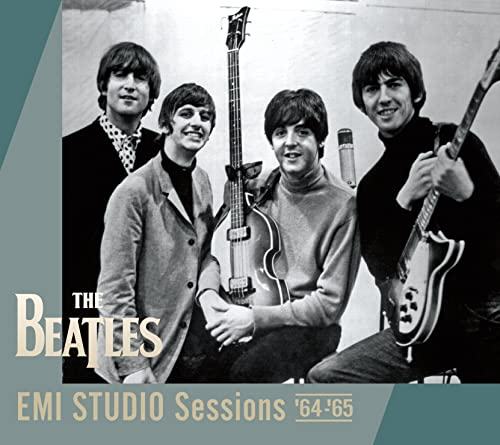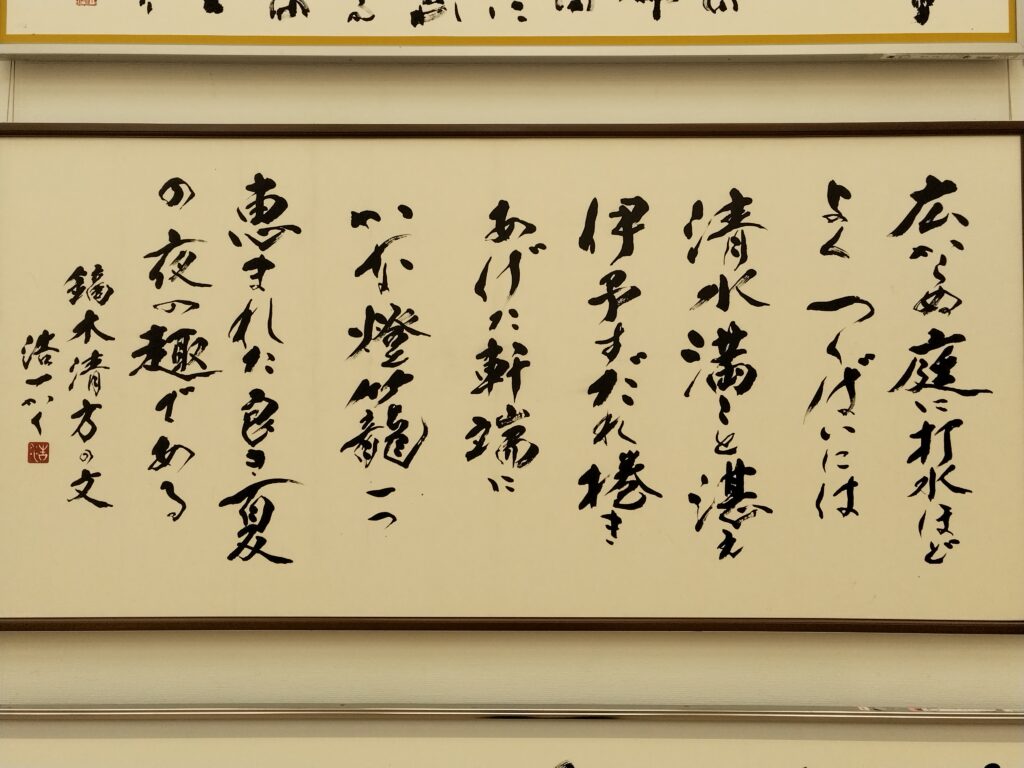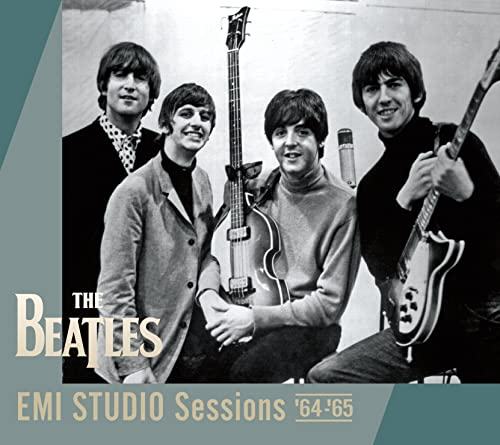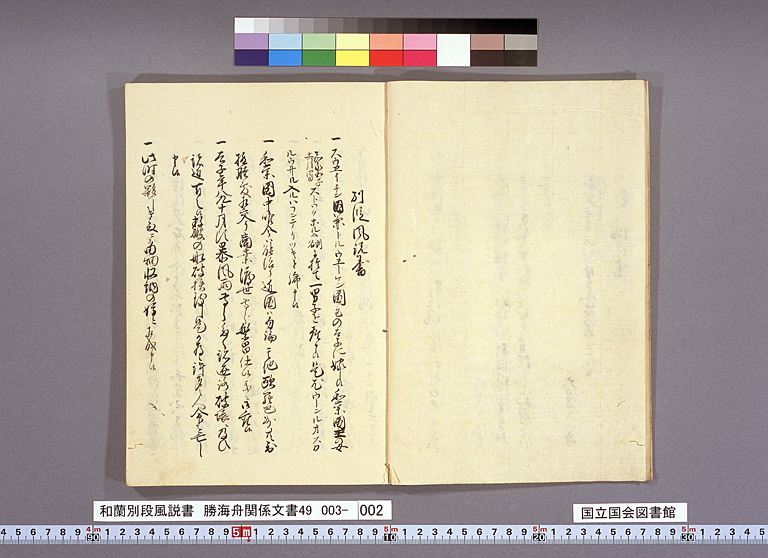山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2024年8月 トピックス】
横浜・関内のカラオケスナック
ビートルズをこよなく愛する職場のN先輩の誘いで、8月中旬には店を閉じるという関内のカラオケバーに行ってきた。
私も学生時代にはビートルズのまねごとをしたこともあり、嫌いではない。
我々一行にはもう一人、ご婦人がいた。
先輩の親戚でN.瞳さん。プロのジャズシンガーだという。彼女もビートルズマニアを自認している。
初対面の方だ。
3人がカウンターに座った。
店にはギターやベースが置いてあり、ライブショーをすることもできるのだという。店が狭くキーボードは外に出してある。
N先輩はビートルズマニアで、1966年のビートルズ初来日の時は大学1年。武道館での公演をナマで聞いたという御仁で、ビートルズの話をしだすと止まらない。
その先輩のイチオシが店のマスターだ。
マスターは学校卒業後、数多くの人材を輩出した一流企業に就職したものの、ビートルズ好きが昂じて会社を辞めたという。
◆リバプール
そのマスターが8月下旬、世界中から、厳しい選考をパスしたビートルズのコピーバンドがリバプールに集う「インターナショナル・ビートルウィーク・フェスティバル」に日本代表として出場するという。
もちろんギャラもなく、交通費も出ない。名誉だけでリバプールのステージに立つのだ。
(為替の関係で今年のリバプール行きは、多少こたえるかもしれないが)
このため店は8月に閉めるものの、愛媛での開店準備に入るのが遅れるという。
◆「Oh, Darling」
マスターはステージで主にベースを弾き、ポールのパーツをやるという。
「これを歌えるヤツ者は日本ではほとんどいない」いうポールの曲を歌ってもらった。
「Oh, Darling」
キーはかなり高いが、歌いこなしている。かなりの迫力だ。
オリジナルキーのままで歌えることを羨ましく思う。
ポールもいまだ現役で、オリジナルキーで歌っている。
私はキーを2度、場合によっては3度下げないと歌えなくなってしまった。
マスターはポールのパーツをやっているが、本当はジョンが好きだという。
◆愛媛で新規開店
関内のカラオケバーを閉じてどうするか。
愛媛に行くという。
しかし、松山市ではない。隣町の東温市だ。
なぜ、東温市か。
親戚や身寄りがあるわけではないという。
彼は関東の育ち。奥さんは大阪出身。
義理の母(奥さんの母)が愛媛の八幡浜出身だという。しかし八幡浜からはかなり遠い。
松山市からも車で20分以上かかり、愛媛大学の医学部があるところだ。
横浜から移りたくなり、候補地となる各地を訪ね歩いたそうだ。
京都、奈良、神戸、福岡・・・どうも違う。しっくりこない。
ある時、たまたま東温市に寄ったとき、いわゆる「降りてくるもの」があり、「ここだ!」と決めたという。
私もかつて、愛媛に2年勤務したことがある。
今度愛媛にいった折は、覗いてみよう。
◆ジャズのライブ
後の話。
カラオケバーに一緒に行ったN.瞳さんのジャズライブをYoutubeで聞いてみた。
さすが、堂々たる歌いっぷりで、いい感じ。
一度、ライブに行ってみるのもいいかもしれない。
(学23期kz)