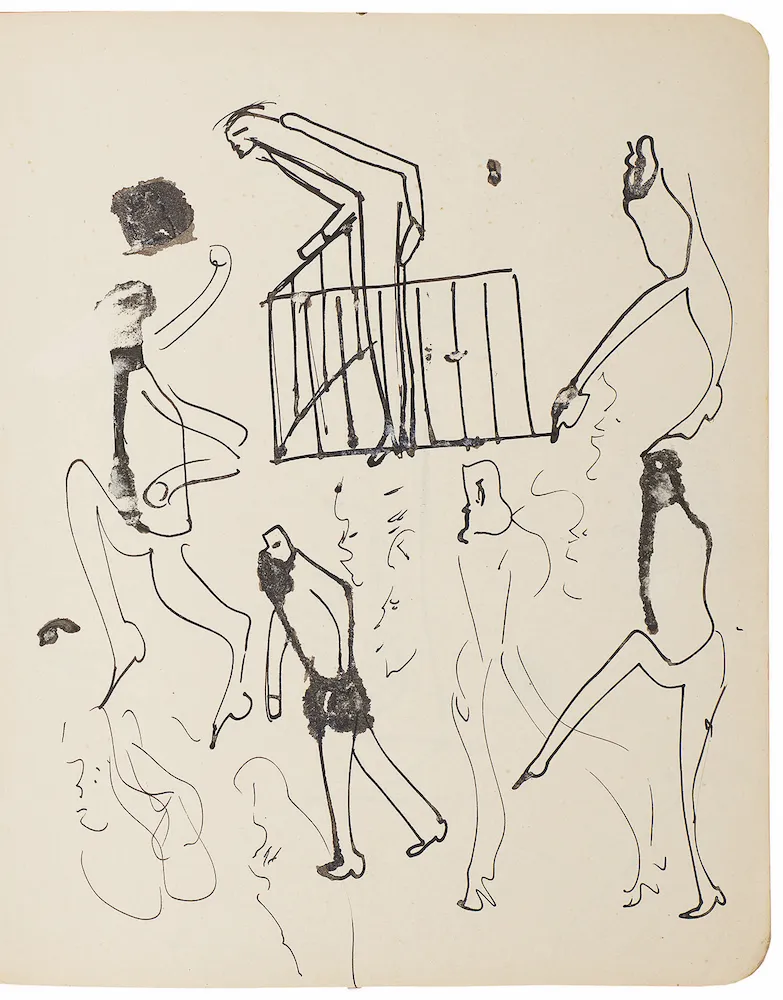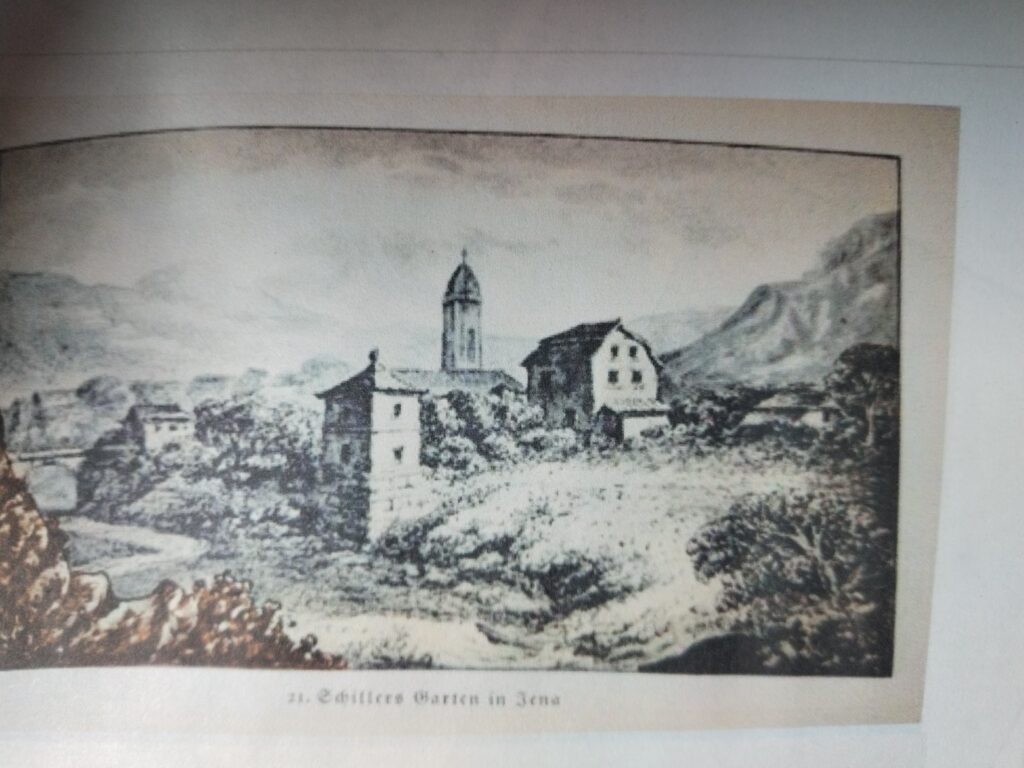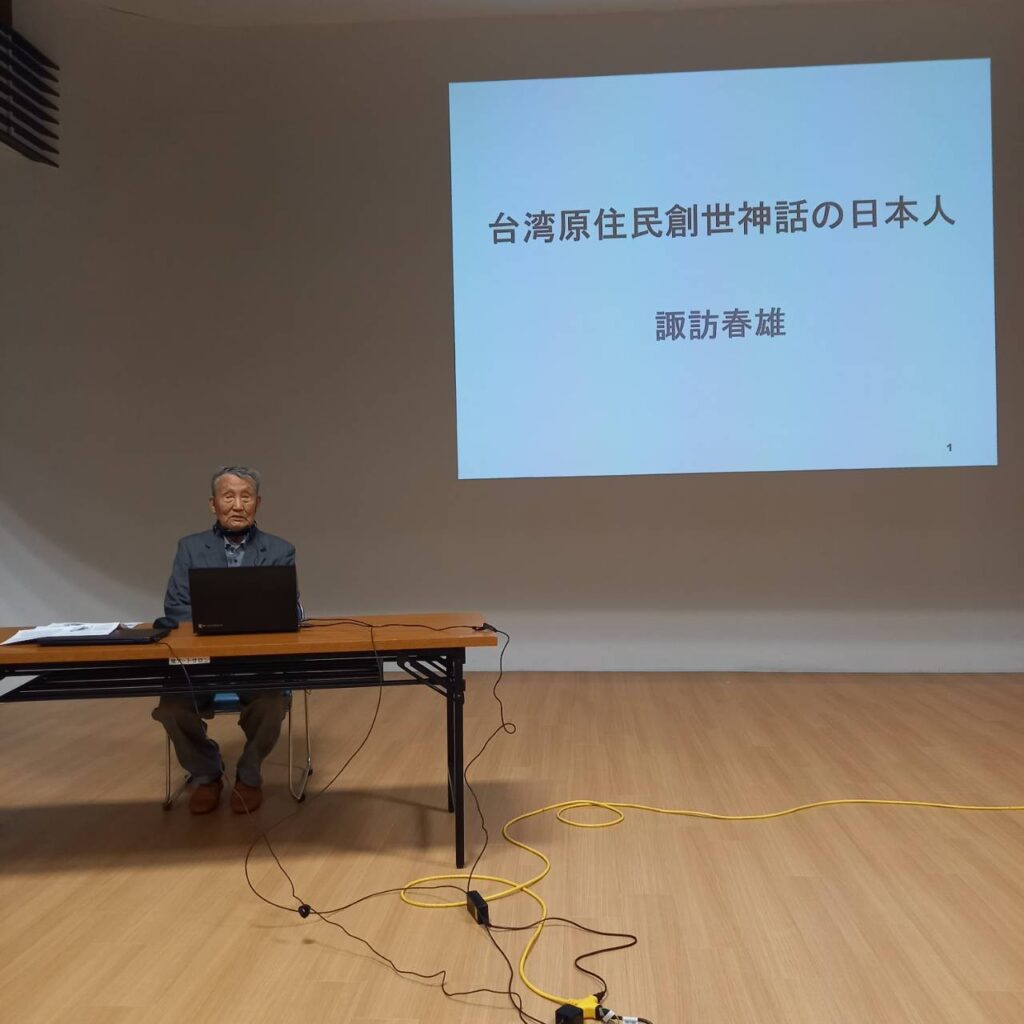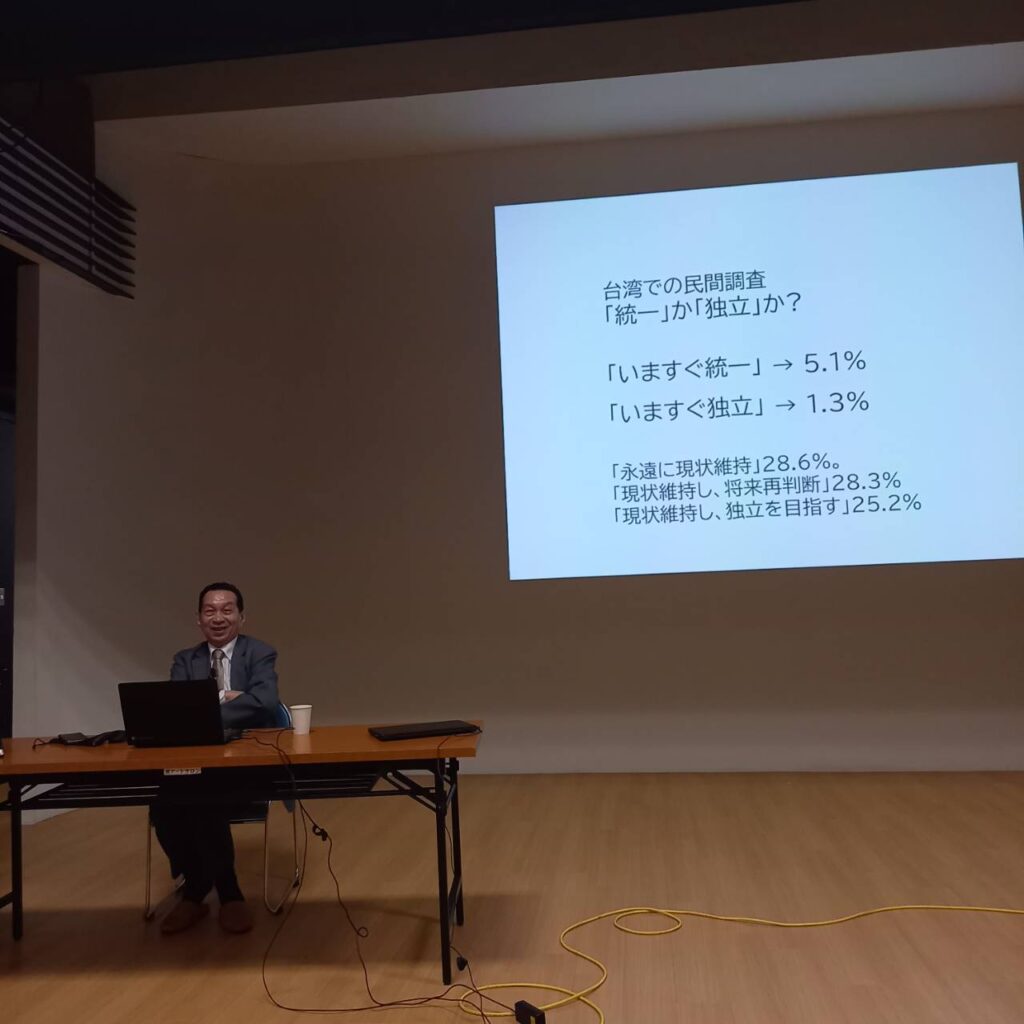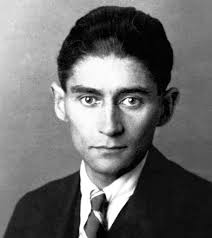山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2026年2月 トピックス】
昨年秋の第6回長州歴史ウォークでは明治神宮、東郷神社を経て乃木神社を巡った。
◆明治神宮御苑内の清正井
明治神宮では東門から右手に憲昭皇太后の御休憩所だった隔雲閣を観、左手には南池(なんち)を観ながら菖蒲田を通り過ぎたところに清正井(きよまさのいど)がある。
ここは加藤家下屋敷の庭園があったところで、井戸は清正公自身が掘ったものとされる。
東京の名湧き水の一つとされ、夏冬通して15度の清らかな湧き水が湧き出ている。
結構な量の湧き水が出、穢れを落とすことから、パワースポットとしても有名になっている。
◆加藤清正公の「ボシタ祭り」
豪傑武将のイメージがある加藤清正公。
熊本には「ボシタ祭り」がある。
「ボシタ、ボシタ」の掛け声とともに飾り馬で通りを練り歩く。
秀吉の命で清正公が関わった文禄・慶長の役で敵を「滅ぼした」ことに由来する掛け声だ。
しかし加藤清正公は単なる豪傑武将ではない。
◆乃木将軍が身をもって知った清正公
他方、西南の役では陸軍少佐だった長州の乃木希典。
明治8年熊本鎮台歩兵大14連隊長心得として小倉に赴任。明治10年に西南の役に政府軍として参戦。
熊本へ向かう途中、2月下旬の夕刻、熊本北部の植木で薩摩軍と戦闘状態に入る。
乃木軍の兵力は200、薩軍は400。
ここで乃木軍の連隊旗を保持していた河原林雄太少尉が討たれ、薩軍の岩切平九郎に連隊旗を奪われる。
厳しい戦いだ。
乃木将軍は、この闘いで、清正公が築いた熊本城への攻略が極めて難しいことを悟り、清正公の偉大さを身に染みて味わったという。
また、4月18日に乃木軍は堅牢な熊本城に入城。
この熊本城を拠点に薩摩軍に勝利した。
西郷隆盛が言う熊本城。
「加藤清正と戦して、勝てんようなもんじゃ・・・」
乃木はここでも、熊本城を築城した清正公の偉大さを痛感した。
つづく
(学23期kz)