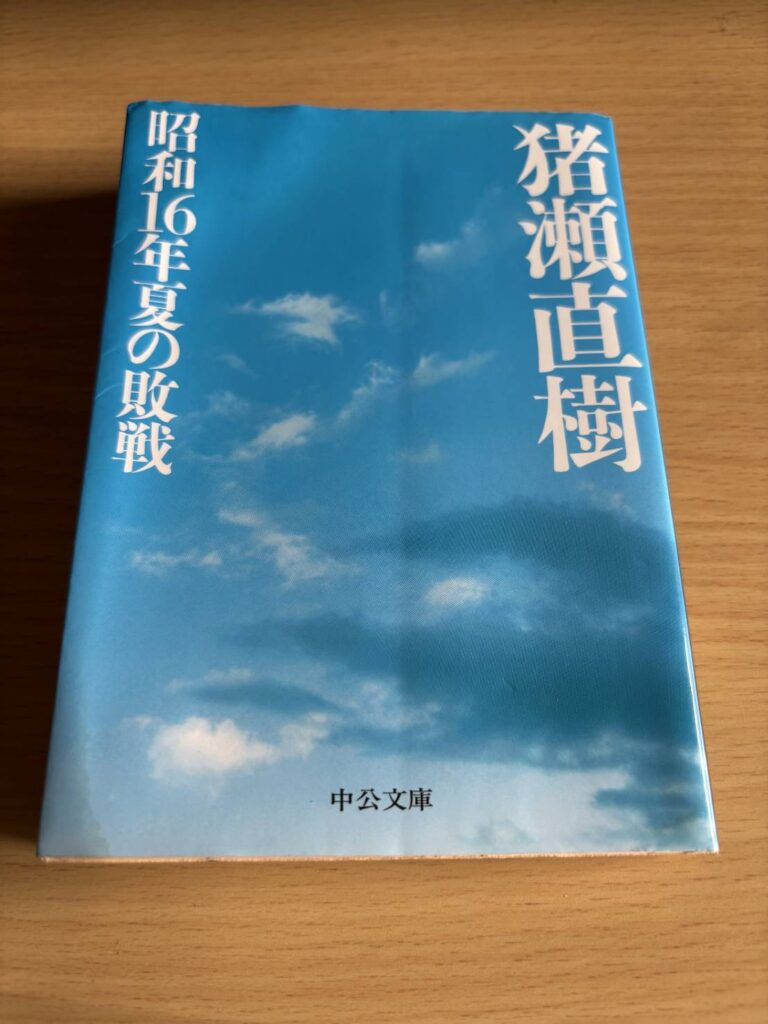山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2025年10月 トピックス】
◆スタグフレーション
経済は時により、局面により効果のある施策が変わる。
不況時には有効だったケインズ政策が通じなかった出来事が生じた。
オイルショックで生じた不況下のインフレ、スタグフレーションだ。
不況を克服すべくケインズ政策を行えばインフレを伴いがちだが、時はすでにインフレ状態にある。
こうした時にケインズ政策をとるのは適切ではなく、インフレを加速させる。
◆新自由主義
フリードマンの思想にあるのは政府の裁量による規制などの恣意的な施策をなくし、企業や個人が自由に自発的に経済行動を行った方が国全体の経済パフォーマンスが上がるとした。
このため、国のスローガンとしては「減税、規制緩和、民営化」など経済を自由化させるものであり、ケインズの施策が「大きな政府」なら、フリードマンの施策は「小さな政府」であり。
こうした小さな政府は1980年代のレーガン、サッチャー時代に流行し、日本では三公社を民営化した中曽根政権の時代に当たる。
◆政府の役割
ここでの考え方は、政府を「不要」とする無政府主義ではなく、政府には企業や市民が自由に行動できるよう、各種規制や制限を撤廃し、動きやすい市場になるような、「市場の監督者」という役割を与えている。
フリードマンは、1929年の大不況は金融当局が金融政策を誤ったとし、政府は安定した通貨供給を行うように提言している。
◆フリードマン(シカゴ大)などの、新自由主義のシカゴ学派は、ケインズ主義のように、政府は施策を講じるべきという積極派なのではなく、恣意的な施策を講じるべきではなく、市場に干渉するなという規制・干渉撤廃策といえる。
私の現役時代は、こうした「自由な市場の有効性」の信奉者は、官庁では経済エコノミスト集団である経済企画庁に多かったように思われる。
なお、市場における政府の役割について、消極的に捉える新自由主義に対して、やはり政府は完全ではない市場に能動的に働きかけるべきとする「ニューケインジアン」もいる。
代表者が、クルーグマンであり、スティグリッツ。
両名ともノーベル賞を受賞している。
(学23期kz)