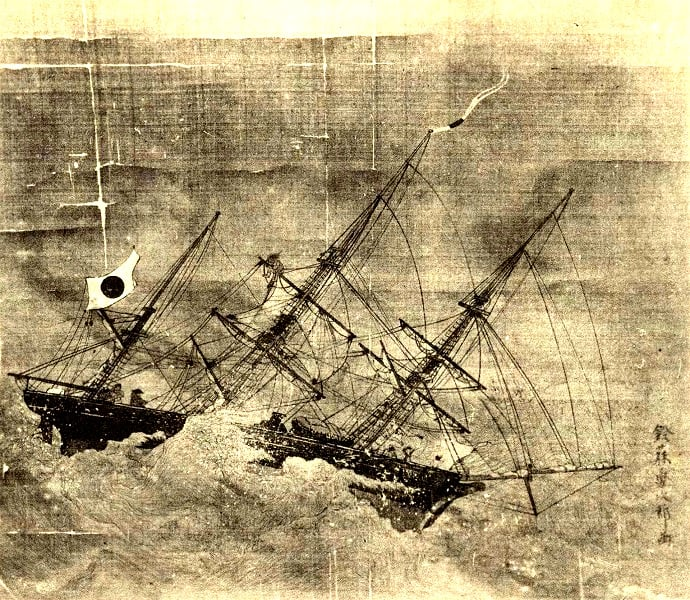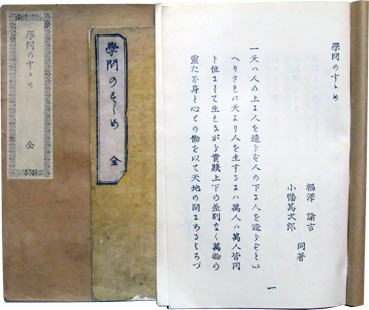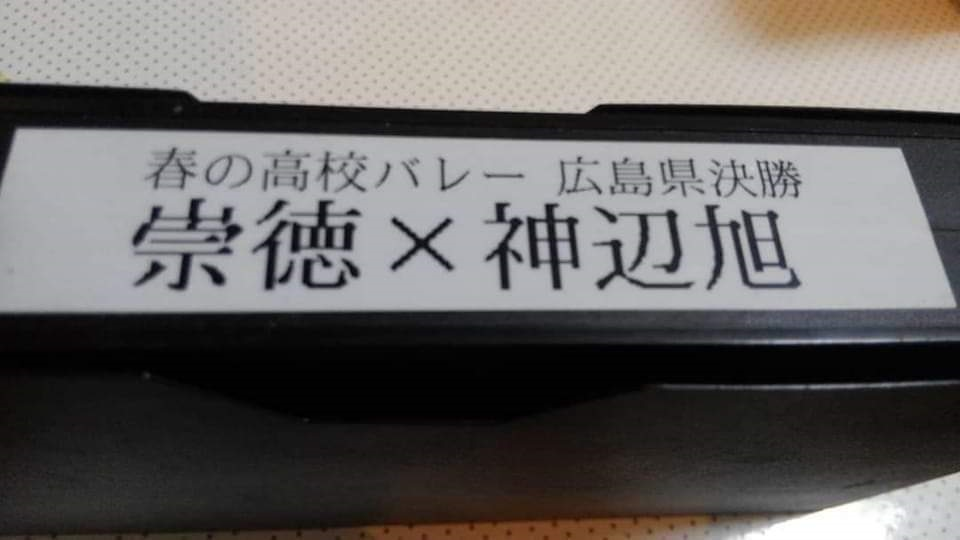山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2023年 9月トピックス】
現在の親世代は昭和の時代。彼らが身を置いたのが「年功序列、終身雇用」制度。これは日本の特徴的な雇用慣行として、世界的に経営学の研究対象となった。日本の勝れた経済パフォーマンスを生み出す制度要因と見られたからであった。
◆年功序列、終身雇用
この用語は米国の経営学者ジェームズ・アベグレンが1958年に初めて使い始めた「lifetime commitment」の訳であり、1950年~60年にかけての高度成長に伴う労働者不足への対応から始まったのだ。歴史は浅い。
アベグレンといえば日本の経営指導者のファンが多く、「日本的経営」という言葉を定着させた有名人だ。
戦後、輝かしい高度成長を遂げた日本経済。この時には会社経営の中心に年功序列があり、終身雇用があった。
この時代、会社に入れば先輩が仕事の仕方、他の部署や取引先との接し方、会議の進め方を手とり足とり教えてくれた。OJTだ。
また、アフターファイブになると飲みに連れて行ってくれた良き時代であった。
こうした時代は人口減への転化、バブル崩壊、IT革命を機に壊れていった。
企業のパフォーマンスの低下に伴い、福利厚生が削られ、給与も据え置かれ、終身雇用も維持できなくなった。
過去の人気企業も名前が変わり、姿を消している企業も多い。中央省庁の名前さえ頻繁に変わるようになったのだ。
評論家の中には子供の就職や転職に際してのアドバイスに関して、受験勉強では答えではなく答えを導く考え方を教えるようにと、また取った魚を持ってくるのではなく、魚の取り方を教えるべきという者もいる。
しかし、魚の取り方が変わってきているのだ。
また、「すべてのものは消えゆく中で、その奥の永遠なるもの、真の価値あるもの」を子供に伝えよという。
しかし、この「永遠で真の価値」と思われたものも、不透明で流動的であり、価値が簡単に逆転する場合が往々にして起こるのが現代だ。
◆親の教訓
年功序列・終身雇用の下で働いた親世代の意見は、変化が激しく、雇用の流動性が高まった時代には参考にならない場合が多い。
場合によっては親のアドバイスが「誤り」となる可能性もある。
これまで会社人生を過ごしてきて我が子に気の利いたアドバイスをするのが難しい時代になった。
◆親の教訓の有効性
親にとって、自分が生きた時代の経験が全てである。
日本が輝いていた(と思われる)昭和の時代。
この時代は日本の経済史の中では特殊で、かなり短い時代であったかがわかる。昭和の経験から子への教訓を引き出すことには留意が必要だ。
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」(ビスマルク)。
自らの経験から教訓を導くには限界があることを戒めなければならない。
現在は新しい世界。ビジネスも変わった。
古き良き日本が得意とした安くて品質の高い製品を大量に生産することができるように磨き上げた従来型製造業中心の世界が大きく変わり、従来一過性の産業と思われていた情報産業が世界を覆い、モノづくりの世界を大きく変えようとしている。製造業の最高峰・自動車産業で電気自動車が出てきたように。
新しい世界は、親にとって馴染みのない世界であり、自分の時代の経験を伝えることの有効性には大きな疑問符が付く。
親は親としての意見を述べても良い。専門性、経験・実績、信頼関係(人的資産)、協調性の重要性は伝えるべきだ。
しかし、子供にアドバイスをするときには、自分の経験、特に自分中では評価してきた現役時代の成功体験、その有効性にこそ限界があることを認識することを忘れてはいけない。
少し寂しい気がするが・・・
(学23期kz)