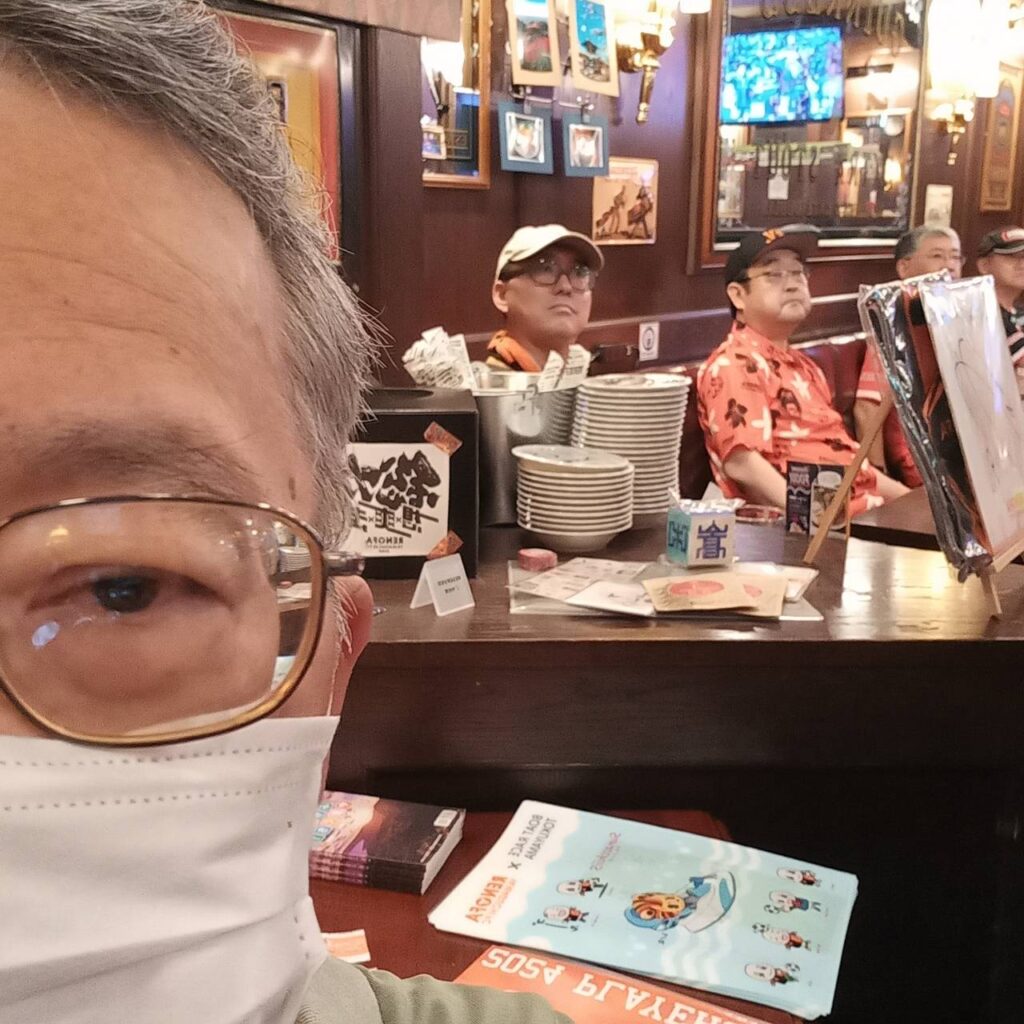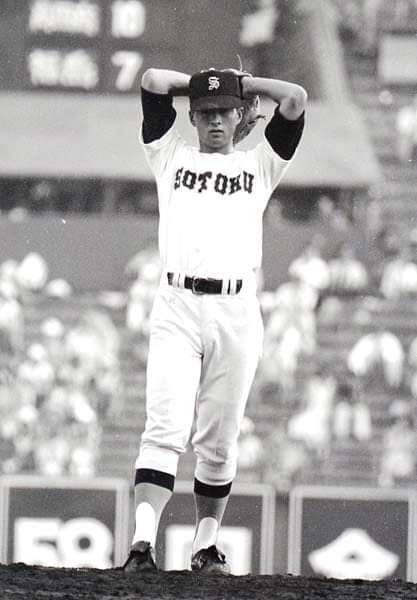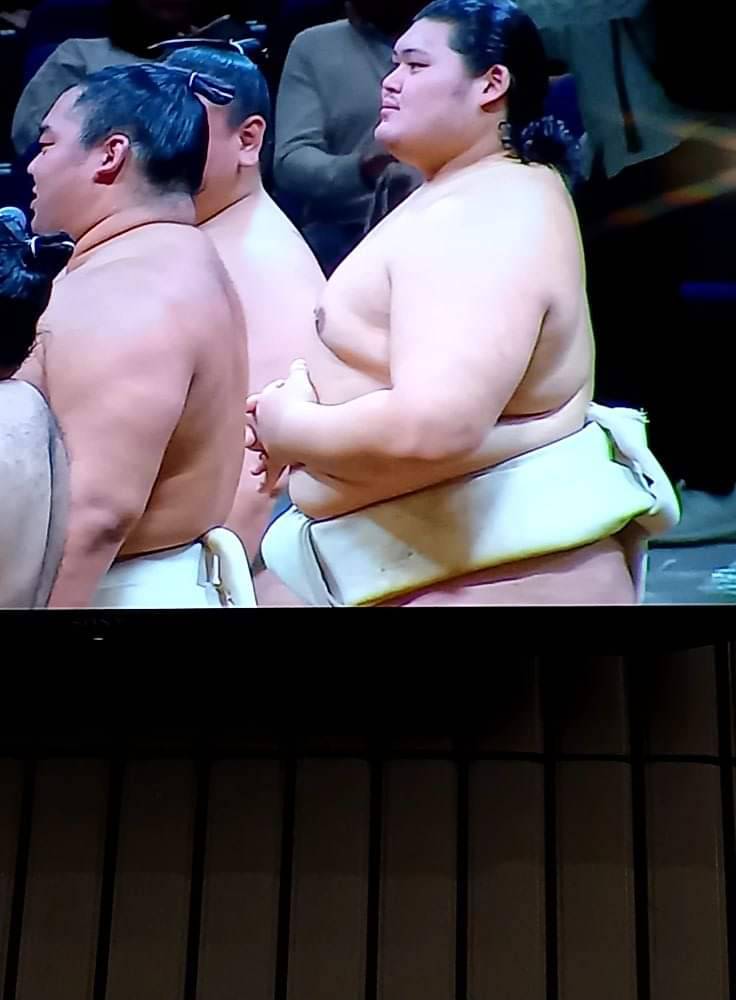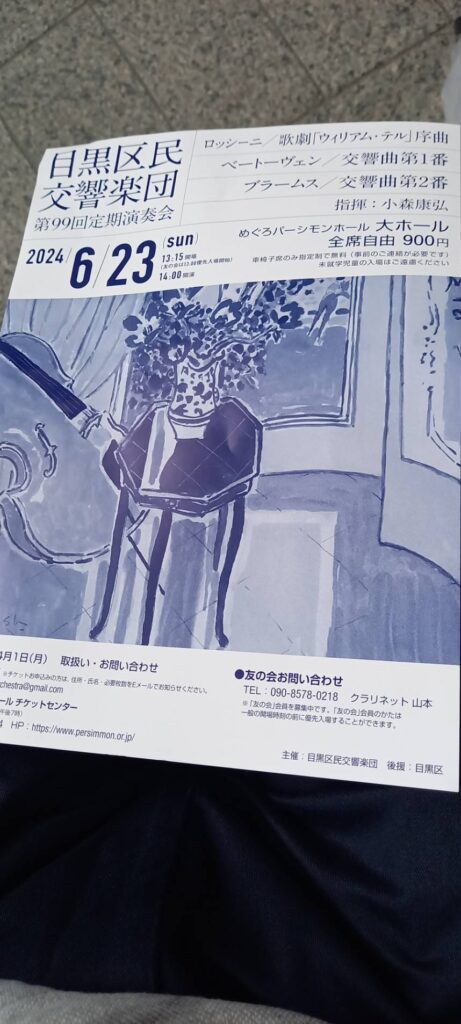山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2024年 6月トピックス】
前稿では、総論賛成でありながら、なぜ改革が進まないかを考えてみた。
言うまでもないが、そもそも改革の機運生まれた時に、総論反対を唱える者もいる。
すなわち、改革論が出た時に
・それでどうなる
・失敗したらどうする
・誰が、どう責任を取るのか
・・・よく聞くセリフだ。
これらは改革の機運に冷や水を浴びせるもので、改革を封印する殺し文句でともいえる。
こうした議論への対応は別の機会で述べるとして、この稿では総論賛成でありながら、なぜ改革がうまくいかないか、特徴的なケースを挙げて検討する。
ここでいう総論賛成とは、すなわち表面的には総論に反対してはいない場合も含まれ、実はここに問題が潜んでいる場合が多い。
◆改革頓挫
各論で賛成が得られないケースをみてみよう。
当初、改革が具体的にどのような形で自分の身に影響が及ぶか読み切れておらず、議論が深まるにつれて自らへのマイナスの影響が可視化される場合
同じ会社内で事業分野が統合され、垣根が取り払われると、各部門の情報が共有されることになる。
この場合、自ら苦労して集めた経験や情報が新たな仲間に「タダ」で供与され、共有されることに不快感を示す場合がある。
改革のやり方、改革の方法論にも拘りが出る。
改革に賛成でも改革のやり方に執拗な拘りがあれば、改革そのものに反対に回ることが往々にして起きる。
業績を上げるには、不要な業務、生産性の低い業務、旧態依然とした業務をしている分野から、新たな分野、生産性の高い分野、世界と競合できるような分野へ経営資源を集めることが必要になる。
この時にそうした分野への人材のシフトが必要になるが、リスキリングを含め、自己変革を迫られる働き手の抵抗が始まる。
◆中間管理職に多いリスキリングへの消極姿勢
日本の企業で指摘されているのが、社員が学び直しをせず、リスキリングの意識が低いという点だ。
しかも、こうした層は中間管理職に多いという。
少し古いデータになるが、我が国の大手人材系シンクタンクがアジア・太平洋地域14か国を対象に2019年に行った「
就業者の就業実態・成長意識調査」では東南アジアやインドでは、社外学習・自己啓発が活発で自己研鑽に意欲的であったが、日本は「とくに何も行っていない(学ぶことをしていない)」と回答したのは、およそ半数にあたる46.3%。各国比較でも日本が突出して高かったという結果が出ている。
◆厄介な「沈黙(サイレント)層」・・・沈黙はカセ(枷)なり
改革を行う場合、より深刻な問題は、ぎりぎりまで意見を言わず、なかなか正体を現さない「沈黙(サイレント)層」が多く存在する点だ。
彼らは改革論議に際し、意見を言わない。
ある程度しっかりした意見を持っている者でも、自分の意見をつまびらかにしない。
実に奥ゆかしい。
しかし、改革論議の際にはこれが困る。
その理由はいろいろあろう。例えば・・・
・自分が「出しゃばり」のレッテルを貼られるのを嫌う
・議論に慣れておらず、意見を述べることが恥ずかしい
・直属の上司の顔色を伺う
・他部門との衝突や他部門からの批判を恐れる
・自分の改革案で成果が上がるか否か不透明で、自信がない
しかし、こうした層は総論が通るまで、みんなの前ではダンマリを決め込んでいるが、実際に改革が実行されそうになり、自分の身に自己変革が要求される改革の波が押し寄せてきそうになると、途端に反対の声を上げる。しかも猛然と。
これが問題だ。
ここでトップがリーダーシップを発揮し、反対派を説得できば問題ない。
しかしリーダーが大所高所の見地から改革をリードしようとしても、役員を始めとする社員の改革意識が低い場合、議論が空回りする。
改革論議の漂流だ。
こうした場合、議論をもう一度スタート時点、すなわち総論からやり直すことになる。
こうした例が身の回りにあまりに多いような気がする。
政治の世界や役人の世界しかり、一般企業の場合もそうだ。ひいては身の回りの自治会、マンション理事会などなども同様だ。
これに比べ、戦国時代は異なる。
時代劇、特に戦国時代の議論の風景をみると、賛成、反対に分かれて実に真剣に意見を戦わせる。
何も脚本家が場面を盛り上げるためにいたずらに激論を戦わせる場面を盛り込んだのではないように思う。
戦国時代、主張することはしっかり主張しないと、己の身があっという間に物理的に滅びることになる。すなわち死に直結しているから真剣に意見を言い、議論を戦わせる。
◆沈黙(サイレント)層の意見を引き出す匿名web会議
コロナ時代に流行ったweb会議がある。
名前を伏せて会議に参加できるのだ。
恥ずかしがり屋が多い日本人には、場面によってはこうした匿名web会議が有効に機能することがあるのではないか。
こうしたツールを用いれば総論の賛否を議論するときから、意見を開陳する垣根が低くなり、上司や他部門の顔色を伺うことなく議論できる。本音の主張が増え、議論が活発化することも期待できる。
重鎮が揃う役員や幹部会でも有効かもしれない。
匿名web会議が改革に効率的に辿り着く有効な意見交換の場となるよう、運用の仕方を磨くことも面白い試みではないか。
(学23期kz)