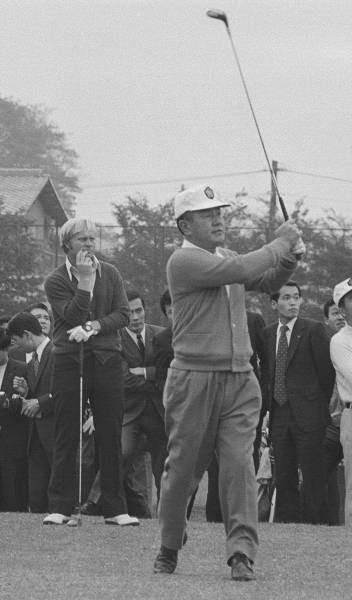山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2025年11月 トピックス】
◆北前船
越荷方の稿では北前船について触れた。
上方と蝦夷地を結ぶ西回り航路で、船主は各地の港で商品を仕入れ、商品を売りながら大きな利をあげ、寄港地の港では北前船が持ち込んだ産品で生活の質を上げていった。
蝦夷地の昆布の普及が和食文化を変えたのもその例の一つで、また鰊の搾りカス「鰊粕」が綿花栽培を行う毛内の肥料として需要が膨らみ、その交易で莫大な利益が生じたとされる。
◆名を売った二人
北前船でこうした利益を手にした廻船業者の双璧が工楽松右衛門と高田屋嘉兵衛だ。
この両者では高田屋嘉兵衛が有名だ。
司馬遼太郎の「菜の花の沖」の主人公にもなった。
高田屋嘉兵衛は淡路島の貧しい家に生まれながら秀逸な操船技術を身に着け、天才的な目利きで蝦夷地を舞台に偉大な廻船問屋に成長し、露ゴローニン事件の当事者にもなった有名人だ。
他方、高田屋嘉兵衛より26歳年上の工楽松右衛門の名はあまり目にしたことがない。
◆工楽松右衛門の生き方
兵庫・高砂に生まれた工楽松右衛門も廻船業者で、北前船で大きな利益を上げた。
しかし、工楽にはこうした商才があっただけではなく、別の顔を持っている。
ひとつは発明家。
木綿の編み方を工夫した丈夫な帆(いわゆる松右衛門帆)を考案し、これによって船の走行性能を大幅に上げることが可能となった。
また、工楽が偉いのはこうした独創的な帆の編み方を自分だけの技法として秘匿することなく、求める者には伝授している。
太っ腹だ。
もうひとつの顔。
築港や船の船渠(ドック)という、船に必要なハードのインフラの築造も行なう施工事業者だ。
ここでもまた、築造技術の伝授を請われれば、その技法や運営方法を技惜しげもなく伝授したという。
ここでも太っ腹。
幕府の港湾構築依頼にも応じている。しかも自費持ち出しでの対応だ。
発明・考案や船舶補修・港湾築造技術の研磨・蓄積。
こうした面に優れた者として、幕府から「工楽(くらく)」という姓を賜ったという。
「工(たくみ)を楽しむ」、「工夫を楽しむ」ことを指す。
◆公の益、天下の益
個的利益を遠く越えて、天下の益に尽くす気高い理想を持った工楽松右衛門。
なかなかできることではない。
松右衛門が残した言葉がある。
「人として天下の益ならんことを計らず、碌々として一生を過さんは、禽獣にも劣るべし」。
耳が痛い言葉だ。
(学23期kz)