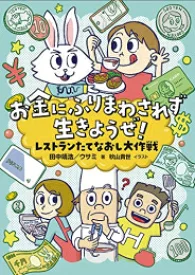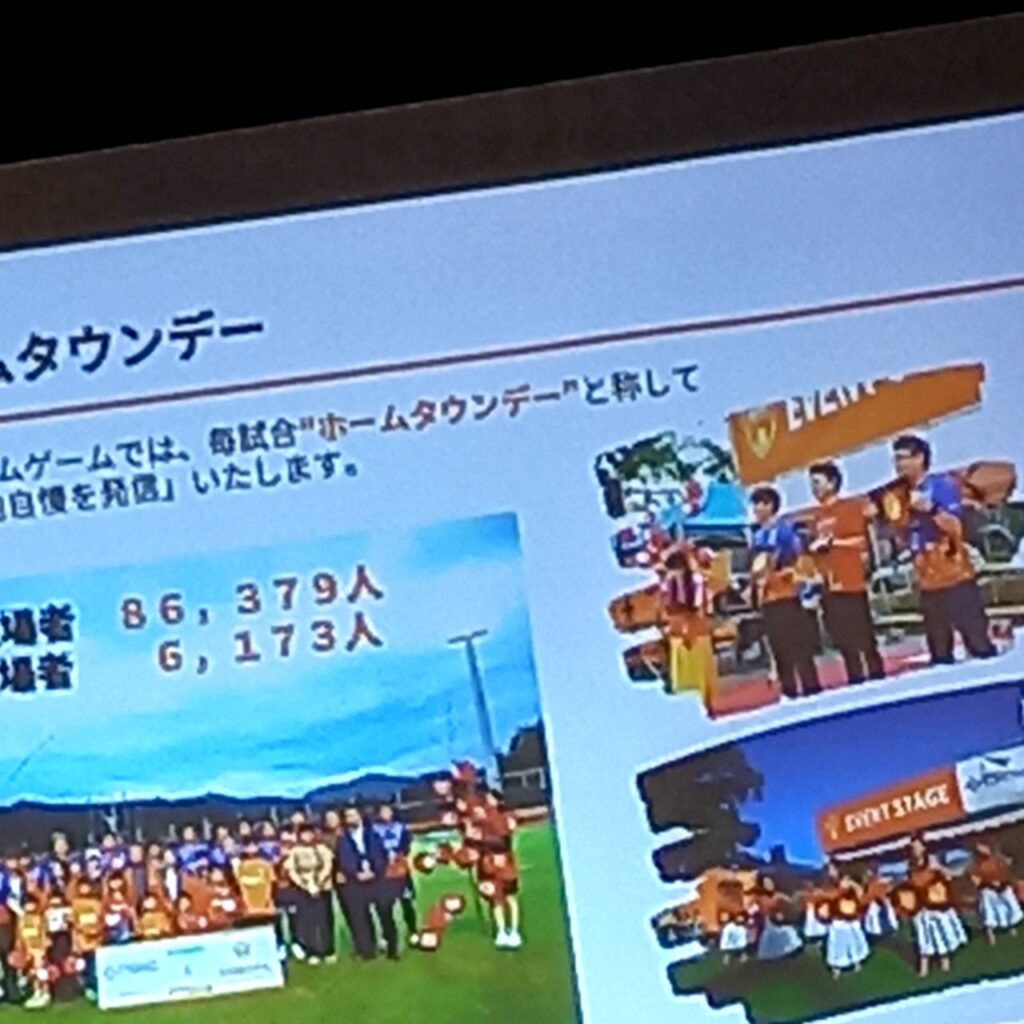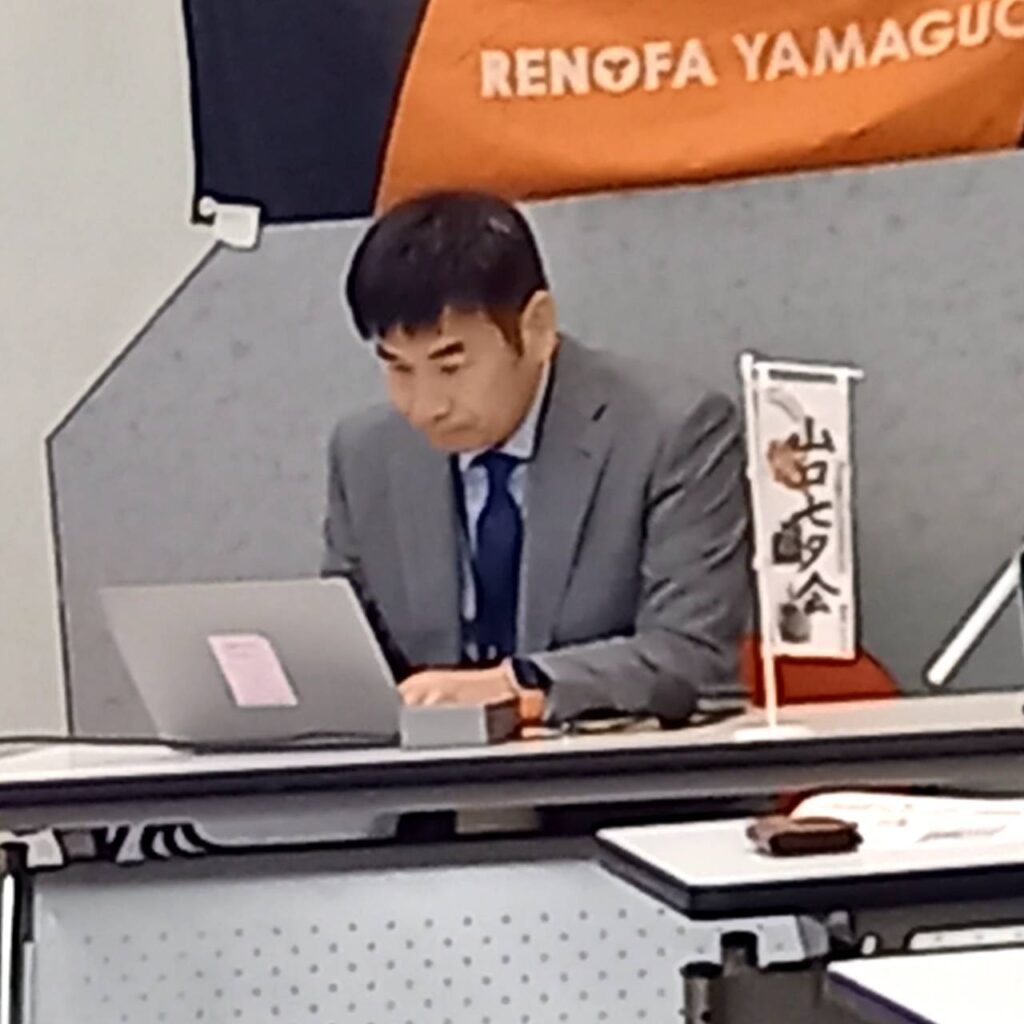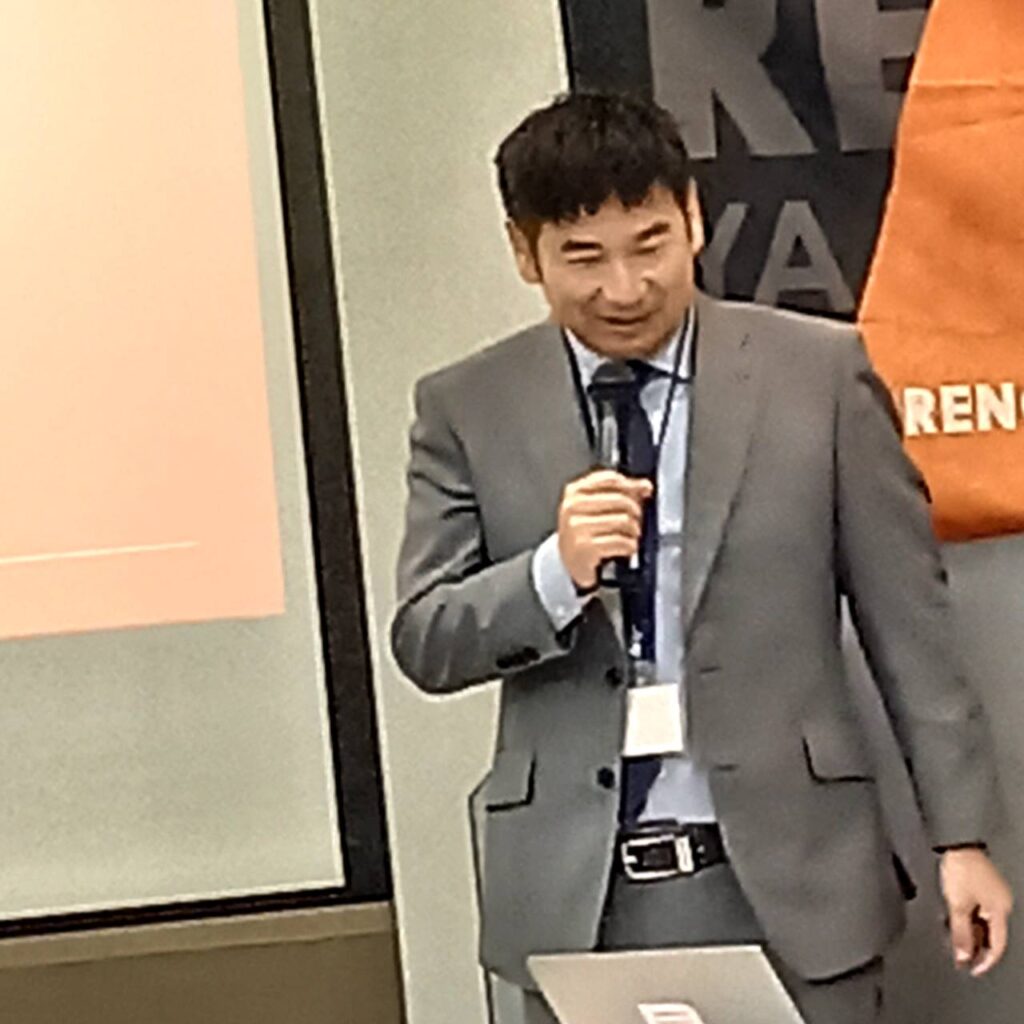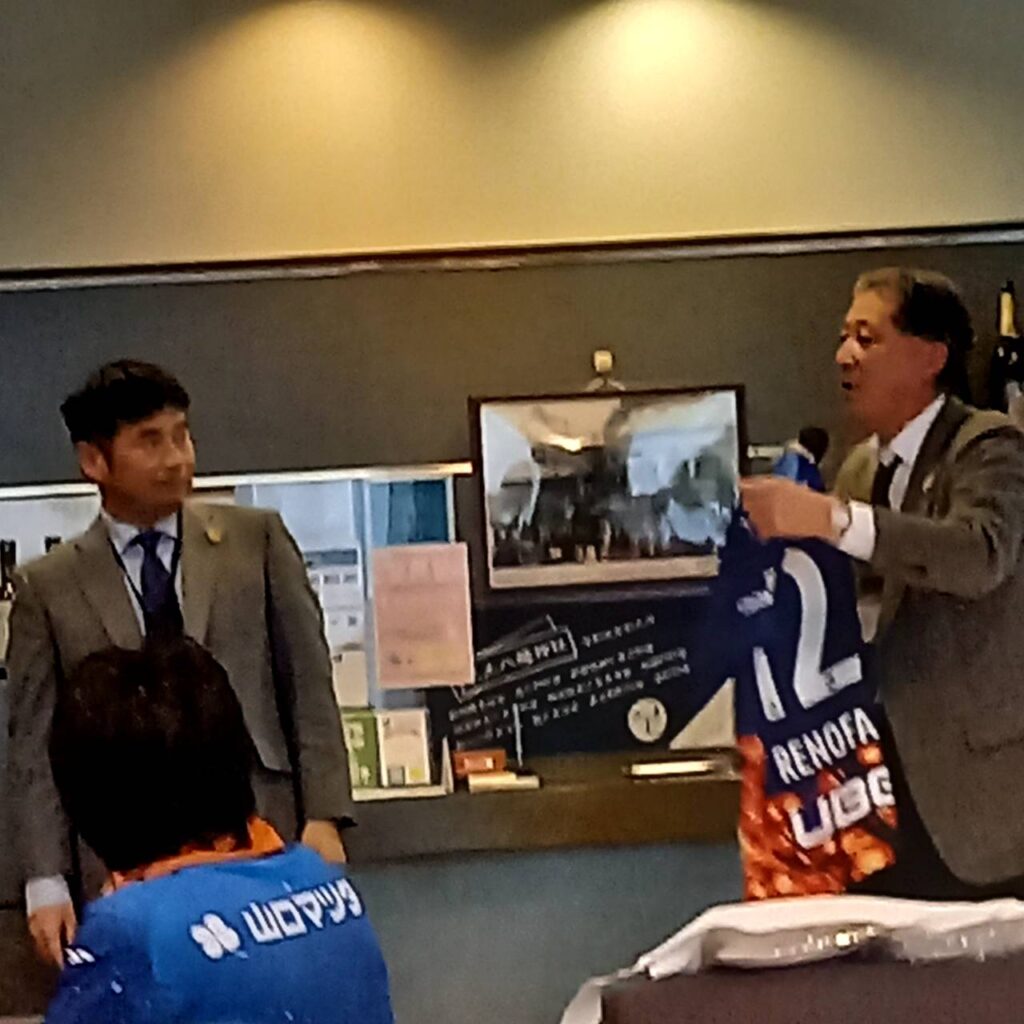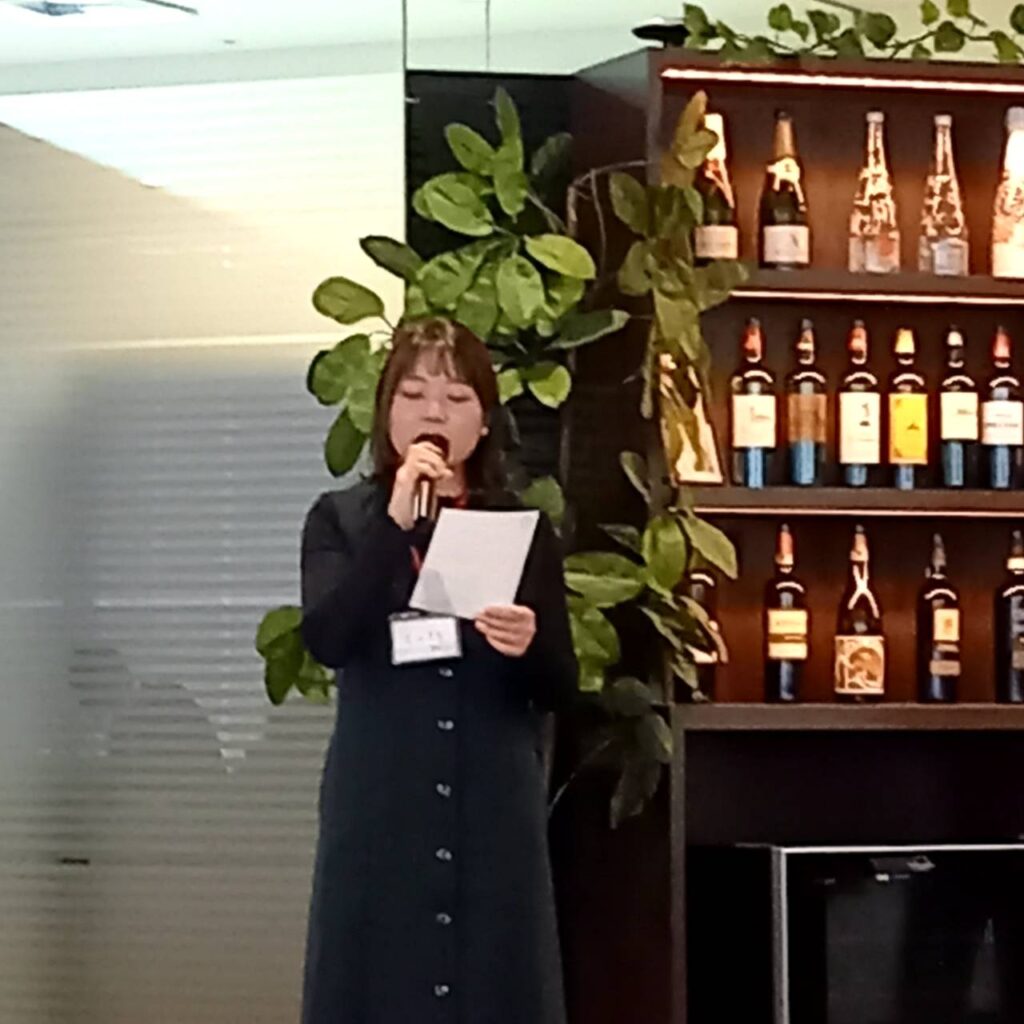山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2023年 12月トピックス】
今年はペリー来航170周年ということで、東京湾では記念クルーズも行われている。
170年前に戻ろう。
東インド艦隊司令官ペリーが黒船に乗ってやってきた。
蒸気船サスケハナ。
カタカナで書くと日本語であるかのような響きがある。
Susquehanna
ネイティブ・アメリカンの言葉で、米国北東部を流れる「広く深い川」の意だという。
それが転じてその川(hanna)の流域に住みついた部族をサスケ(susque)族と言うようになり、サスケハナはその地域一帯の地名となったようだ。
ペリーが浦賀沖に現れたのが59歳の時。
米国が太平洋岸まで達する領土を得ることとなったメキシコとの戦争。ペリーは来航直前、このメキシコ戦で活躍している。
メキシコとの戦いが勝利のうちに終わり、ペリーの艦隊勤務の残り日はわずかとなった。
ペリーは名門海軍一族の生まれであり、その誇らしい海軍軍人キャリアの最後を飾るポストとして花形の地中海艦隊司令官を希望していたという。
しかし、豈図らんや日本行きの任務が回ってきた。
異国に門を閉ざしてきた手強い日本。その門を叩き、こじ開けるのだ。
厳しい任務になるのだろうが、「日本を開国に導いた歴史の偉業」として刻まれることをペリーは意識し始めた。
日本研究のためにシーボルトの著作を読み、日本と交流のあったオランダの駐米高官から日本の情報を入手していたという。
また、蒸気船の早期導入を主張し「米国海軍蒸気船の父」と言われたペリーだ。メキシコ戦で発注した大型蒸気船ができた時には終戦を迎えており、この船の活躍の場を求めていた。このため日本に向かう艦は大型蒸気船と決めていた。
また、ペリーにはもうひとつ密かな野望があった。
彼は植物のコレクターでもあった。鎖国日本には植物の雑種が少なく、「自然選択」による進化により、島国日本で新品種の植物が発見できるかもしれないと考えていたようだ。
米国人ぺりーからすると、長く鎖国をし、交渉も一筋縄ではいかない、かたくなな日本を開国させたことは「偉業」であったかもしれないが、他の列強国からすると、やんちゃものに「してやられた」感覚だったのかもしれない。
第一次のペリー来航時の翌月、露プチャーチンが開国を求めてやってきた時、プチャーチンは幕府の指示に従い、紳士的に長崎で交渉を持った。
これに対しペリーは、来航が禁ぜられた浦賀に踏み込み、いきなり高官との面談を要求し、江戸湾内の測量まで行っている。
ずいぶん無茶をやったものだ。
こうしたことから、当時のペリーは西欧各国から評判がよろしくなかったという。
ペリーの二度目の来航時、日米和親条約が締結され、ペリーは日本の開港を手繰り寄せた。
その時、ペリーが用いた対日交渉の切り札が「友好よりも恐怖」だったという。
アジア研究、日本研究の結果辿り着いた着想だったのだろう。
大型の黒艦、世界最新技術を集めた巨艦の蒸気船を背景とした圧力外交。
ペリーの体躯もこれまた巨漢だ。身長1メートル95。日本側の記録にも「六尺四五寸」とある。
当時の米艦乗組員の中でもペリーがひと際大きく、米海軍の日本行きの人選で、日本に威圧感を与えるために、敢えて巨漢のペリーを選んだという話もある。
友好よりも恐怖による威圧外交の源流がここにあった。
ペリーは晩年、日本遠征記の執筆に力を注だ。日本に来た時には身体の相当な無理もあったのだろう。巨漢のペリー。晩年には身体もかなり悪くなっており、アルコール使用障害、痛風、リウマチを患っていたとされる。
ぺりーは日本を去った4年後の1858年に63歳で召された。
(学23期kz)