山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2023年6月トピックス】
6月17日(土)に宇部で全国総会が開催された。
松野元理事長を始めとする逝去された諸先輩方への黙祷で始まり、松永理事長からは各支部で続々と総会が開催されているとの報告があった。
各支部とも4年ぶりにようやく通常の形で総会が開催され、賑やかな懇親の場が戻ってきており、特に最北の北海道支部でも総会が再開されたことが紹介された。北海道支部は会員が13人。会員の柱は旧北海道拓殖銀行とのことだ。最北の北海道の地でも総会が開かれたことは喜ばしい。支部長は木村氏。私と同期だ。
また、総会では有村経済学部長から最近の経済学部の子学生たちの様子が紹介された。
- ラサール出身の山根教授のご活躍もあり、山大全学の中で経済学部の英語のコミュニケーション能力が他学部よりも上がっていること、
- 経営学科の職業会計人コースも好調で毎年現役の公認会計士の合格者を出しており、今般海外の留学生の中から現役合格者が出たこと、
- 歴史のある経済系の学生を対象とした学術大会である全国ゼミナール大会で山口大学のゼミ生が最優秀賞をとったこと。すなわち2022年度の証券ゼミナール大会では兵藤ゼミ(金融経済)の学生が最優秀賞を取り、経済ゼミナール大会では、川村ゼミ(労働経済)の2チームが同時優勝を果たしたようだ(山大経済学部ホームページ参照)。実に誇らしい。
総会の後は懇親会。参加者は総勢130名ほど。
会場に入る際に華やかなバイオリン演奏で迎えられた。バイオリン奏者は宇部を中心に活躍されているプロのバイオリン奏者で、常盤会(工学部同窓会)のメンバーの奥様との自己紹介があった。
来賓は谷澤学長始め理学部、医学部、工学部、農学部の同窓会代表のほか、白石元山口市長(山大院卒)もお見えになっていた。
来賓を代表した谷澤学長の挨拶で、全学同窓会での中枢組織である鳳陽会へ、従前同様、大学への支援・協力要請があった後、乾杯へ。
各テーブルのメンバー同士、テーブルを越えた懐かしの同僚、先輩との名刺交換が行われ、酒を注ぎ交わして賑やかな時間を迎える。
会の途中では留学生を含む学生諸君約20名が壇上に上がり、ひとりずつ自己紹介とショートスピーチをして頂いた。カタコトの日本語あり、英語あり、ほほえましいひとときであった。
最後に次回総会会場となる広島の山下支部長から次回広島総会へ向けたご挨拶があった。
会の終わりに山大学生歌、山都逍遙歌を合唱。
学生時代はあまり学校にあまり顔を出さなかったが、歌を歌い始めると結構歌える。ということは、学生時代、結構な回数みんなと歌を合唱していたのかもしれない。
乾杯には地元小野田・永山酒造の山猿だったが、もちろん「長州学舎」も用意されていた。
(学23期kz)








校歌、逍遥歌の合唱



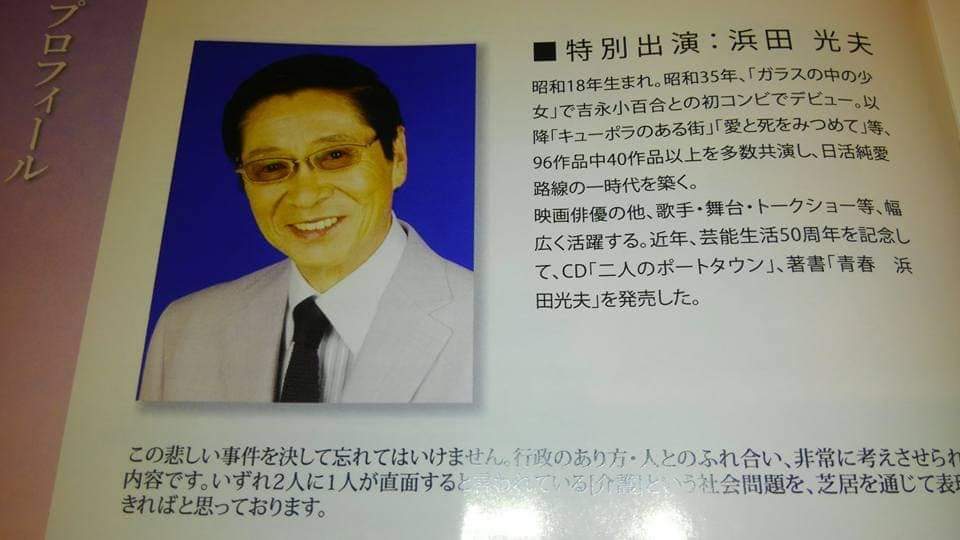



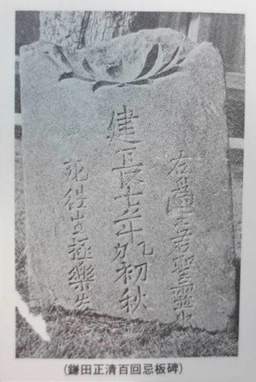



















-1024x768.jpg)









