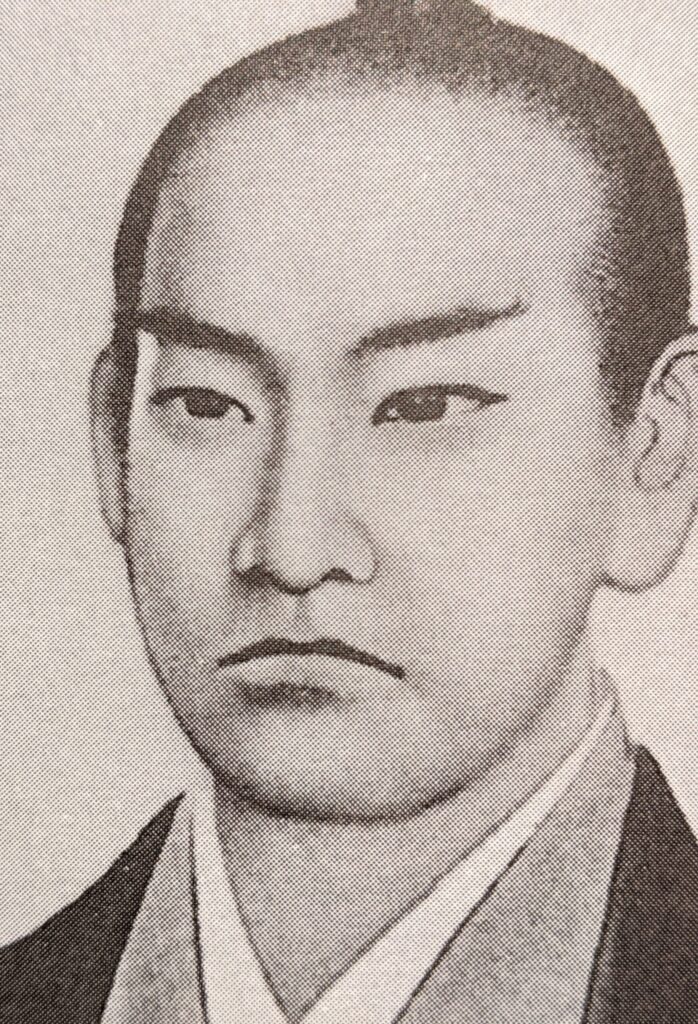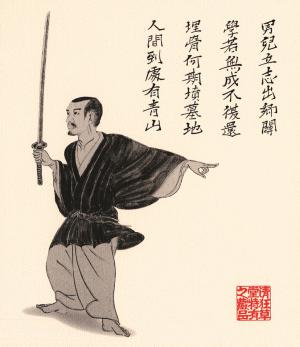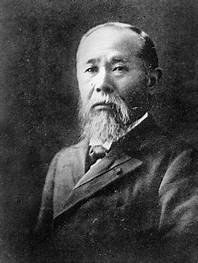山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
【2023年1月トピックス】
目利きが重要であることはいうまでもない。
その道のプロであっても申し分なく目を利かせることは難しい。官民を問わず、計画の策定、プロジェクトの企画遂行はもちろんのこと、人材の採用と選抜にも目利きが命となる。
その眼力によってプロジェクトの成否が左右され、このためプロジェクトに従事する人の人生にも大きな影響を及ぼす。
目利きができる人材の発見と活用、さらには目利きができる人材の育成、これ無くしては日本経済の再生は危ぶまれる。
◆目利き人の育成
ではどのようにして目が利く人材を育成していくのか。
これは官民を問わずどこの業界にも共通する難問で、これができれば話は簡単だ。
この目利きは、特にリーダーの資質として致命的に重要だ。
人はそれぞれ独自の直観力や天賦の資質、独特の個性を持っている。
その発見と活用も重要なことだが、それだけでは足りない。
経験の積み重ねが要る。その経験についても、特定の分野だけで経験を積めば怖いものなしかと言えばそうではない。
周辺分野や全く異なる業界、違う世界を知らなければ、自分たちが置かれた座標軸を客観視できず、適正な判断が下せない場合が多い。ましてや最近は我々を取り巻く環境の変化は加速化・複雑化しており、これまでのビジネス慣行は瞬く間に古くなり、場合によっては間違いとなってしまう恐ろしい時代になった。
こうした中で、今後の展開を予想し、同時代人の発送より常に一歩先を見据えた判断力を養うには何が必要か。
◆フィンランドの事例
以前経済危機に陥った際、官民を含む人材交流の活発化によって目利き人材を育てることにより経済再生を果たしたモデル国があった。森林面積が67%の日本。その日本を超える73%森林に囲まれながら、ノキアを生んだフィンランドだ。
例えば金融機関に籍を置く人物が、特定の期間、大学で研究し、その後、行政の世界でも一定の経験を積み、金融機関に戻るというような事例だ。
誰もかれもこうした経験を積むことは難しいだろうが、中核を担えそうな若者群を選抜し、異質な経験を積ませ、これが各種プロジェクトの成功率を高めたとされた。
お互い別々の業種やサークルに属したままでは、他のサークルのことがよく分からない。こうした状況ではプロジェクトの成功確率が低くなる。逆に、異なる職や近隣の業界の職を体験すれば、土地勘が働き、成功確率が高まることも考えられる。
こうした官民を含めた人材交流は若者や中堅だけではなく、よりシニアな層、考えようによってはトップに近い層の交流も面白いかもしれない。
実際、ヘッドハントなどを通じて、こうしたことは一部実現されているとみることもできる。(つづく)
(学23期kz)
山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
★SNSに登録していただき、フォローをお願い致します。