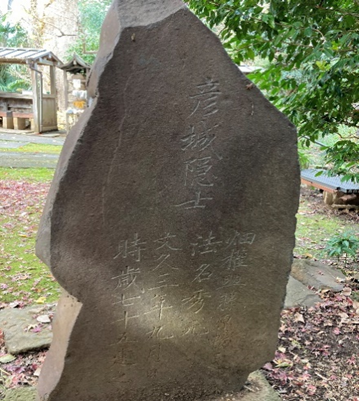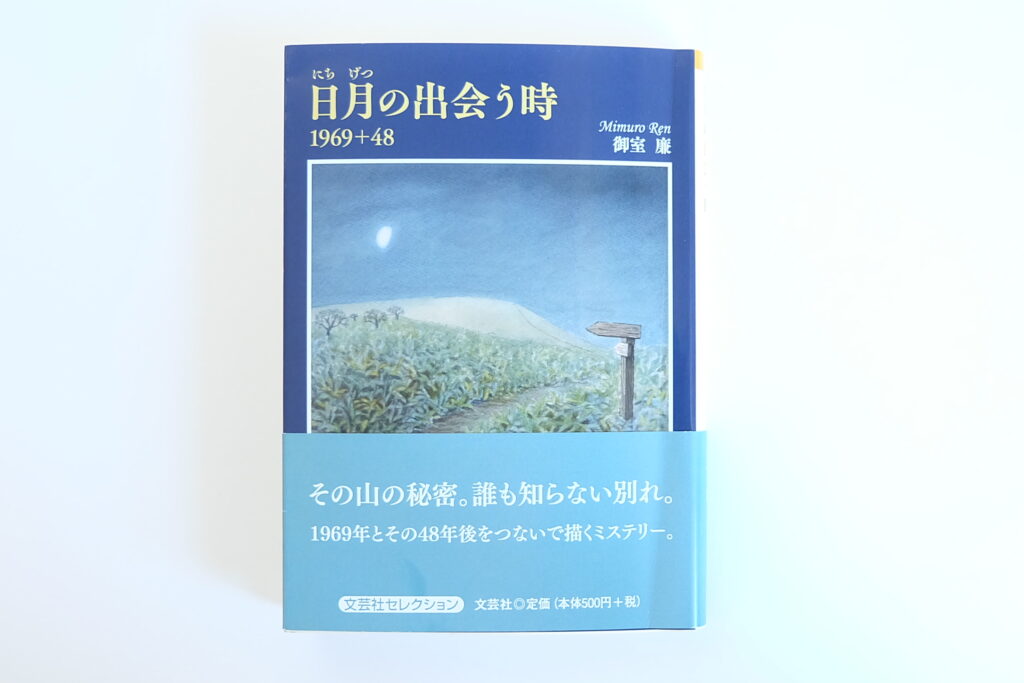本年、緑潤う6月初旬に開催された「第1回長州歴史ウォーク」では長州藩下屋敷があった東京ミッドタウン東の檜町公園に集合、最初に訪れた先が氷川神社であった。
この境内には浅野内匠頭の切腹後、正室・瑤泉院が移り住むこととなった実家三次藩下屋敷があり、また芝居「忠臣蔵」で有名な「雪の別れ」の舞台、南部坂にも足を伸ばした。
赤穂浪士の話は、いつになっても人気が衰えない。この事件については日記や言い伝えも多く残っており、事件そのものが起きたのは事実とされる。しかし、赤穂浪士の話を楽しむには、理詰めで深く考えない方が良いかもしれない。この事件には不可解なことが多いからだ。
もう一度振り返ってみよう。
◇時代背景
事件が起きたのは元禄14年(1701年)春。時の5代将軍で「犬公方」綱吉の時代。貞享元年(1864年)の服忌令(ぶっきりょう)や翌年の生類憐みの令を発し、殺生や無頼行為を禁じる「文治の世」に変えようとした時代に当たる。
赤穂事件が起きたのはこうした令が発出されて15年以上経ったころ。この間人命に関するものだけでなく、身近な動物の保護に関する法令も多く、20年間で350本の令が発出されたと言われている。
嘘かまことか、蚊を叩いて流罪になった者も出たという。こうした中で殿中、しかも将軍、御三家、勅使など地位のある者のみが通ることを許される格式高い「松の廊下」で刃傷事件が起きたのだ。
◇大事な日
この日は、京の朝廷からの使節を迎える当日であった。この勅使使節は綱吉にとって極めて大事な願いの答えを授かる相手であった。綱吉の願いとは何か。儒学を信奉する綱吉が儒学の基本的な徳目である「孝」を尽くしたい母君・桂昌院に「従一位」の位階を授かることであった。
「従一位」の格付けとは。
時の将軍でも存命中は正二位止まりとされ、北条政子でさえ格付けは従二位であった。それに比して位は二つも高い位である。
このため、相場をはるかに上回る位階を得て母君への「考」を尽くしたい綱吉は、このもてなしを何としても成功させたかったはずだ。
また、こうしたもてなしの意味を、主たる饗応役の頭たる高家・吉良公も、また補佐役の浅野公も重々承知していたはず。しかし、あろうことか饗応役の要である二人が、「松の廊下」を血で汚す事件を起こしたのだから何とも不可解だ。
◇湧き上がる疑問
また殺生を忌み嫌う公家の前で、事件を起こしたにも拘わらず、何事もなかったかのように、その翌年に桂昌院には従一位が授けられているから、ますま解からない。
事件は吉良公が立ち話をしていたところ、浅野公が背後から斬りかかったという。武士の習いとして儒教が浸透していたこの時代、年長者で直属の上役を「背後から」斬りつけたのだ。
武士として、ましてや藩の主君として、あってはならない卑怯な行為であるはずだ。
また、浅野公が手にしていた脇差は刃渡り25センチほどのものだったという。脇差の「小さ刀(ちいさかたな)は急所を突いて用いるもの」との常識からも外れており、「討ち損じ」が生じることとなった。
さらに、この時吉良公は刀を抜いておらず、喧嘩両成敗の「喧嘩」にもなっていない。
また、浅野公は吉良公から「いじめ」を受けたともされるが、浅野公は行為に及んだ理由(わけ)を自ら話すことなく、事件から数時間後に切腹と相成ったために、詳細は分からずじまいとなった。
浅野公の使節饗応役は経験を買われての二度目の役回りで、饗応要領も頭に入っているはず。吉良公の「いじめ」に振り回されたとも考えにくい。
こうしたことから、浅野公の「乱心」説が根強く残る。
◇「仇討ち」か
またそもそも論から言えば、四十七士の行動は「仇討ち」とは言わないはずだ。仮に吉良公が浅野公を斬りつけたのであれば、浅野公の家臣・大石内蔵助の吉良邸討ち入りも主君の「仇討ち」なろうが、立場が逆だ。これでは「仇討ち」とは言わず、「追い討ち」ではないか。
◇儒学者達の解釈
四十七士の吉良邸討入りが義挙に当たるか否か。
当時の有識者たる儒学者の間でも意見が分かれたようだ。
四十七士の行動を「罪」として捉え、打ち首とし、切腹さえもさせてはならじ、とする厳しい見方もあった。
しかし、こうした厳しい見方をするのはごく一部の儒者に限られ、多くは、切腹は免れないとしても、主君に対する「忠義」を見せたとして同情する見方が多い。忠義は儒学の重要な徳目であるからだ。
そうした裁きを見せないと、忠義をもって治世する側にとっては困ることになるという判断も成り立つ。
この謎多き赤穂事件と忠臣蔵、なぜ人気が衰えないのだろうか。
◇胸のすく勧善懲悪の筋立て
綱吉については、最近でこそ、文治の世に転換させた名君として評価され始めたようだが、これまでは「犬公方」と渾名(あだな)され、評判は芳しくなかった。特に当時の庶民にとって生類憐みの令は「天下の悪法」と映ったようだ。生活が窮屈になるからだ。飼い犬や飼い猫にも人並みに食べさせる必要が生じたのだから、金銭的な負担も大変だったという。
生類憐みの令を批判した水戸光圀公が綱吉に犬の毛皮を送り付けたのも、当てつけだったのだろう。
生類憐みの令といった、これまでにない法令で縛られるようになった窮屈な時代。
こうした時代にあっては、庶民は胸のすくような話を求める。
弱い者いじめをし、利に汚く、金品に執着の強い者を懲らしめる筋書き。こうした勧善懲悪の筋書きには「悪」の主人公が要る。ここに吉良公が嵌った可能性はある。
いじめる者を成敗したいという勧善懲悪は受けが良い。金品に執着し、賄賂をねだり、私腹を肥やす者には、きついお灸を据える。
特に芝居にあっては奇想天外な場所、ありえない当事者、ありえない筋書きであればあるほど胸がすき、庶民の鬱屈を晴らすことができる。
これが全くの作り話ではなく、実際に起こった事件であればあるほど、面白みは格段に増すのだ。
ここに忠臣蔵の人気が衰えないヒミツがあるような気がする。
(学23期kz)