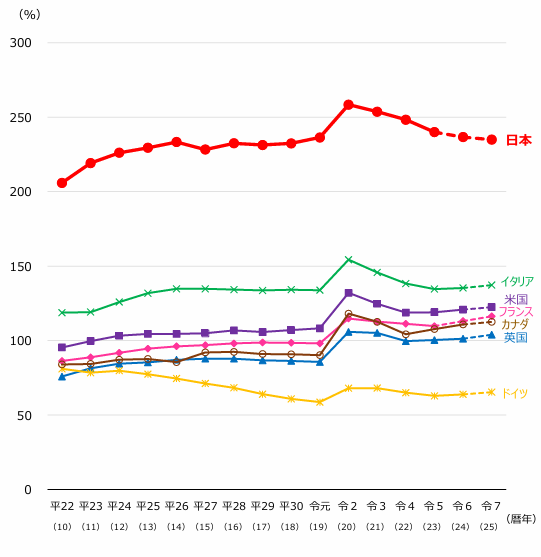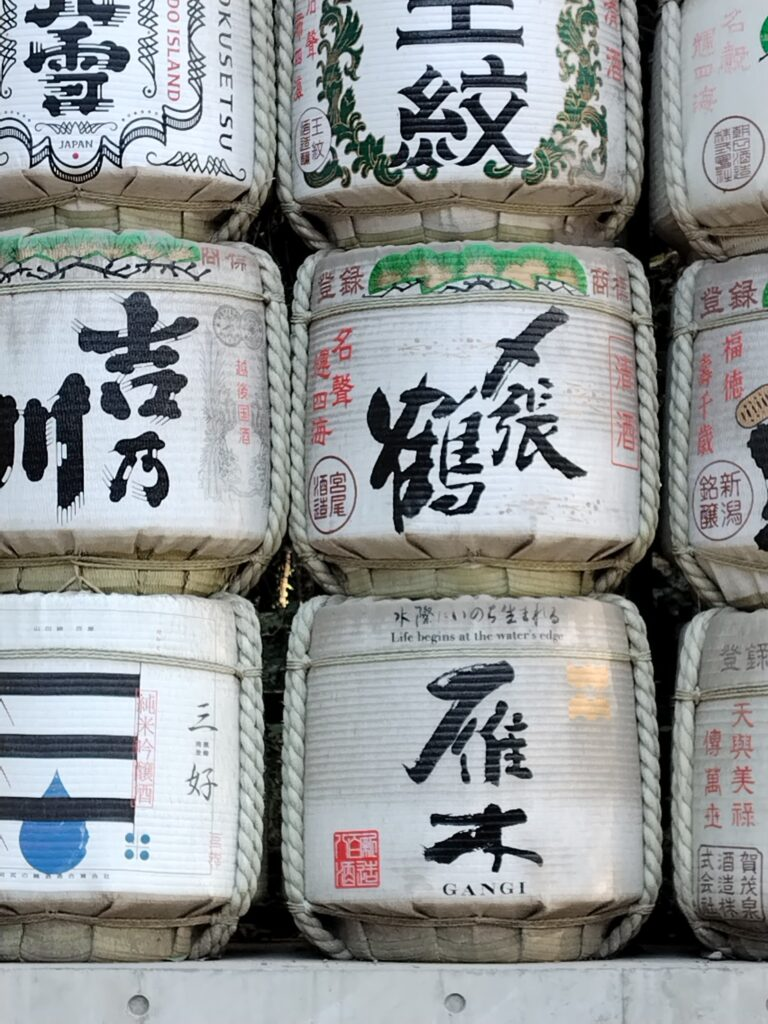山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2025年12月 トピックス】
◆定例幹部会
12月13日(土)、支部長、事務局長のほか、副支部長、監事、顧問が集い、定例幹部会を開催。東京支部の財務改善策を中心に今後の同窓会運営の方向性を固めた。
◆抱える課題
鳳陽会は山口の本部も、東京支部も、似通った問題を抱えている。①若手の未加入、①会費納入率の低迷に伴う財務状態の悪化、③そのための経費節減策の検討、④事務所の移転問題などがそれだ。
◆本部
本部が抱える問題と対応策の検討については、本年10月下旬に行われた理事会の模様を参加メンバーに報告。
財務改善策として、①会報「鳳陽」の発行頻度の検討、②理事会開催の効率化・web化、③全国総会の簡素化、④寄付講座の検証・簡素化などについて討議。
また、亀山にある本部事務所の吉田キャンパスへの移転も大学側や学生と緊密な接触を保つ上で喫緊の重要課題。
そのためには定款の変更が必要となるが、定款変更の議決を容易化・簡便化する代議員制度の導入を検討する。
◆東京支部
東京支部について、この1年間の活動状況を報告。
長州歴史ウォーク、日本寮歌祭、鳳陽ゴルフ会、ホームページの発信強化などを紹介。
こうした取り組みにより、これまで会費納入実績のないメンバーからの新規に会費や寄付を頂戴する機会が増えたことに厚く感謝。
しかし全体的にみると、会費納入率は25%と低迷しており、毎年100万円強の赤字が継続(基金残高は約800万円)。
◆赤字対策の切り札としての事務所移転
赤字解消に向けて、これまで人件費の削減を図ったほか、来年度から始まる本部からの支部支援金を考慮に入れても、約50万円の赤字が残る。
このため最大の費目になっている事務所家賃(毎月10万円=年120万円)の大幅削減を図るべく、賃料の安い事務所への移転を提案(注)。これにより、この先同窓会活動が持続可能な収支均衡化を図ることでメンバーの賛意を得た。
◆このほか、参加メンバーからは会報の発送方法の改善、総会開催会費の安価な会場への見直しなど、経費節減に向けて参考になる意見やアイデアも拝聴。
◆来年の東京支部総会は6月6日(第一土曜)12時から16時。
会場は本年度と同じアルカディア市ヶ谷(私学会館)。
参加メンバーに総会への協力を仰いだ。
(注)【追記・事務所移転】
立地に恵まれた三田の事務所は勉強会や懇親会、討議会場、他学部との意見交換会場、また上京学生の立ち寄り場所などに用いられてきた。
このため、三田からの事務所移転を回避すべく、他学部との統合事務所化、あるいは山口大学の東京事務所化、鳳陽会本部の出先化などの存続策を模索してきたが、万策尽き、移転を決断することとなった。
(事務局)