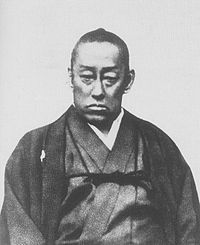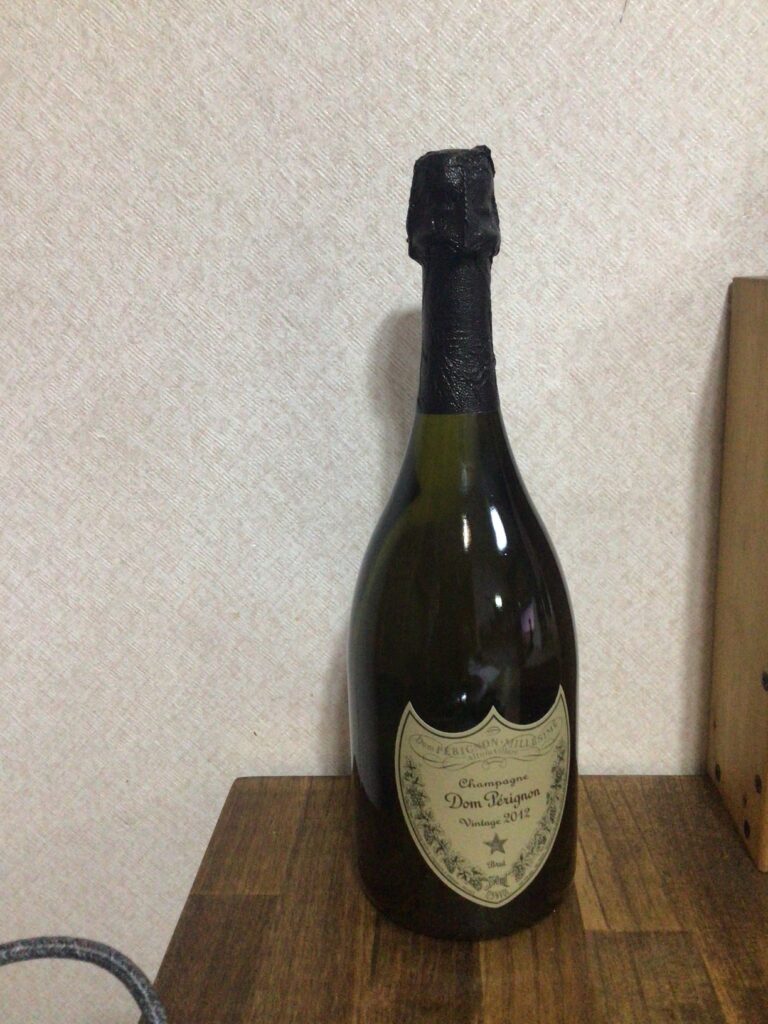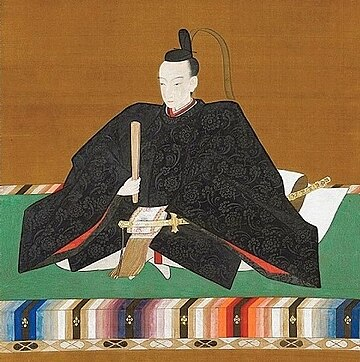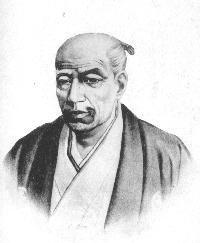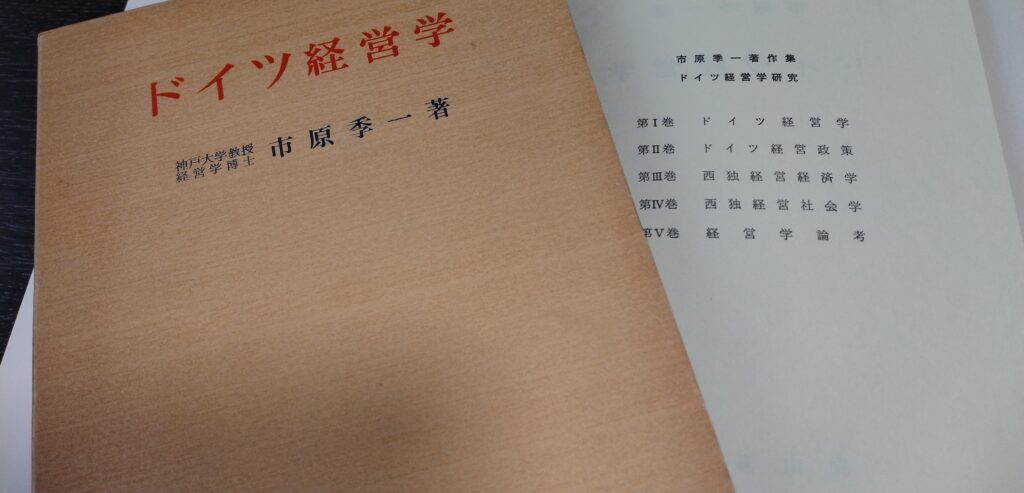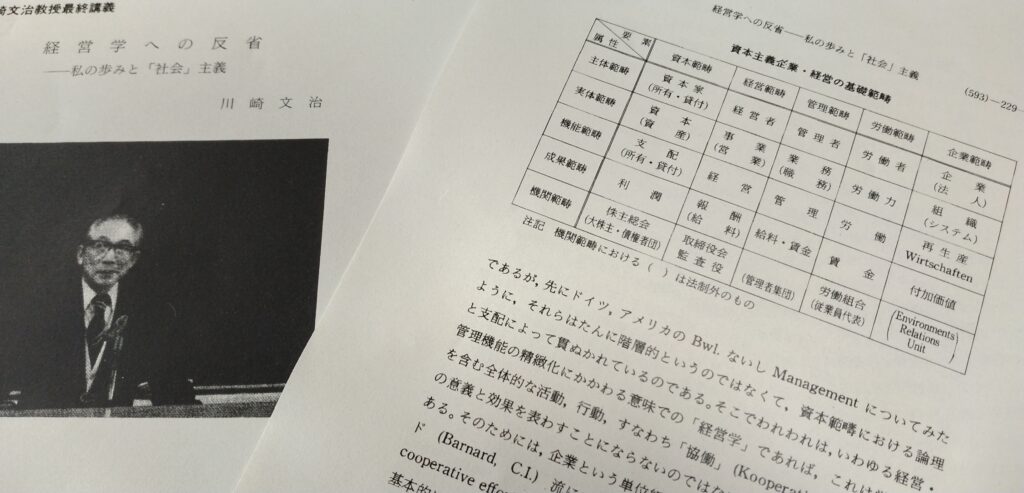山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2025年4月 トピックス】
岡山支部・岡山Bさんの投稿
80年代の初頭のある年、本来授業を受け持つ教官の体調具合がすぐれず、授業開講中止となっても已む得ない中、数名の教官によるリレー方式の講座に変更された開催されたことがあった。(今の大学の講義の中ではある意味よくある設定かもしれない)
微かな記憶では、4名ぐらいの担当教官で運営されたと思われるが、定かではない。
それぞれの先生が、担当科目のエッセンスを各人の数回の授業機会の中で、講義を構成し、教授する。学生もそれを受講するという、当時としては難易度の高いものであったかもしれないと回想する。
最も印象に残っている教官は、財務管理論を担当されていた若き日の赤石先生の授業である。財務管理の基礎の基礎を教授したのち、「ポートフォリオ」と言う話が出てきて、何処か新鮮で、今でも印象に残っている。
ポートフォリオとは、資産を多様化するため、異なる金融商品を組み合わせるということのようだ。社会人になって気づいたのは、リスク分散、また、反対に収益性を図る上でも大切な考え方である。
経営学特殊講義のなかの財務管理で出会ったその理論は、後に勤務先で自己啓発等の通信教育を受講すると事業戦略、また経営管理の中でも当たり前のように「ポートフォリオ」と言う言葉に出くわす。分野の違いこそあれ、あの時、あの六角型の階段教室:大講義室で聞いた話だ。
別の理論編では亀本先生、増田先生も担当されていたかもしれない。経営組織論や労務管理論関係であったかもしれない。記憶は定かではない。
ある意味特殊な事情でやむなく講義内容を変更して開催された、まさしく「経営学特殊講義論」であった。しかし、各先生が研究、担当する授業科目のエッセンスを凝縮して聴講できる貴重な機会となった。
その後、まだまだ未熟な人生の中ではあるが、何度となく思いもせぬ展開で苦境に立つことがあった。しかし、苦境を苦境だと悩み塞ぐことはなかった。あの時の少しピンチであったり、苦境であっても、ものごとの取組み如何によっては豊かな授業につながることを若き日の学生は体得していたのである。
「ポートフォリオ」と言う言葉の効用は、ある意思決定をするときも、時間があれば自分の中で何個かの選択肢を準備する。その中で、その意思決定をする時点においての最適の解、また時の経過と言う時間選好を考えた中での最適の解は何かと自問自答しながら、拙い意思決定をしていった。自分にとって、ある年の「経営学特殊講義」という禍は転じて、福となっている。
(岡山B)