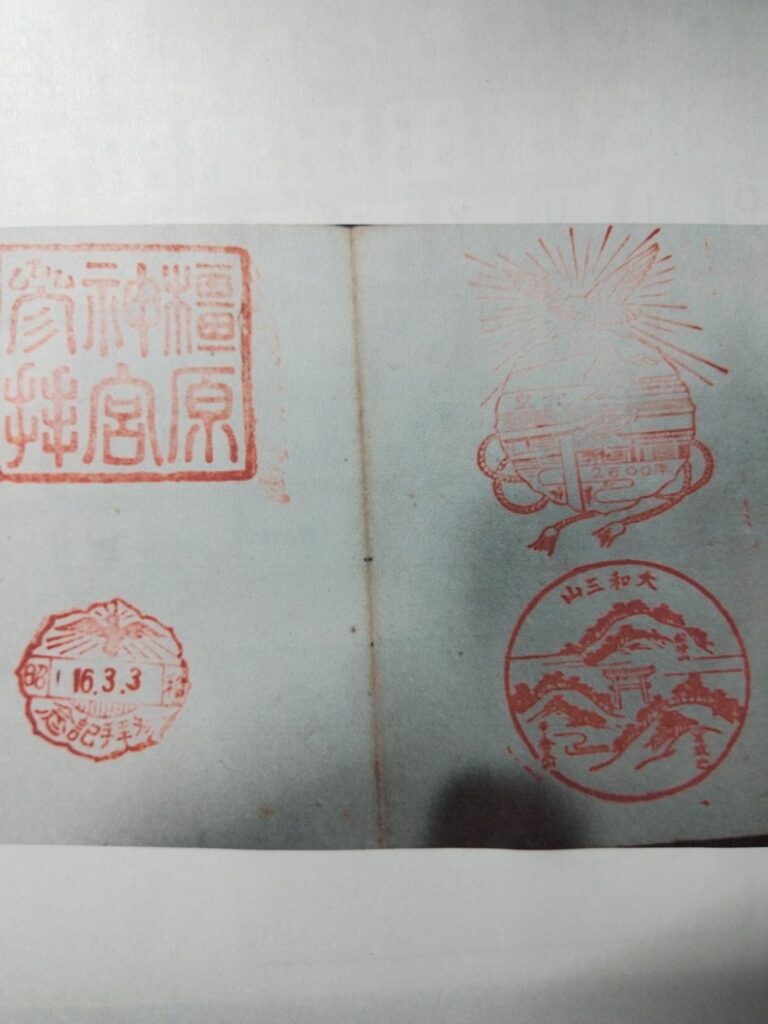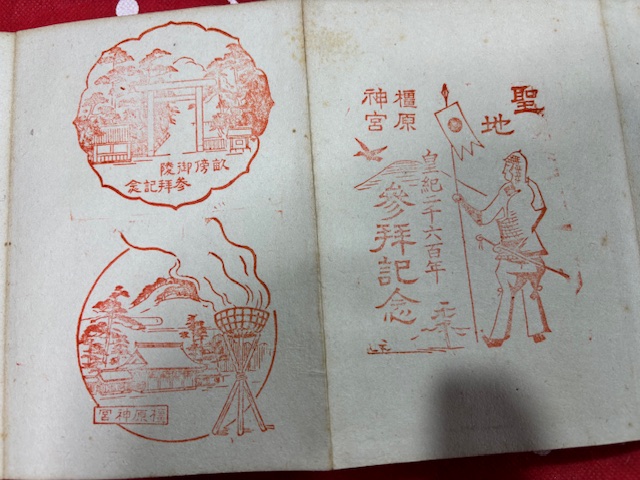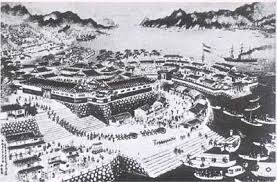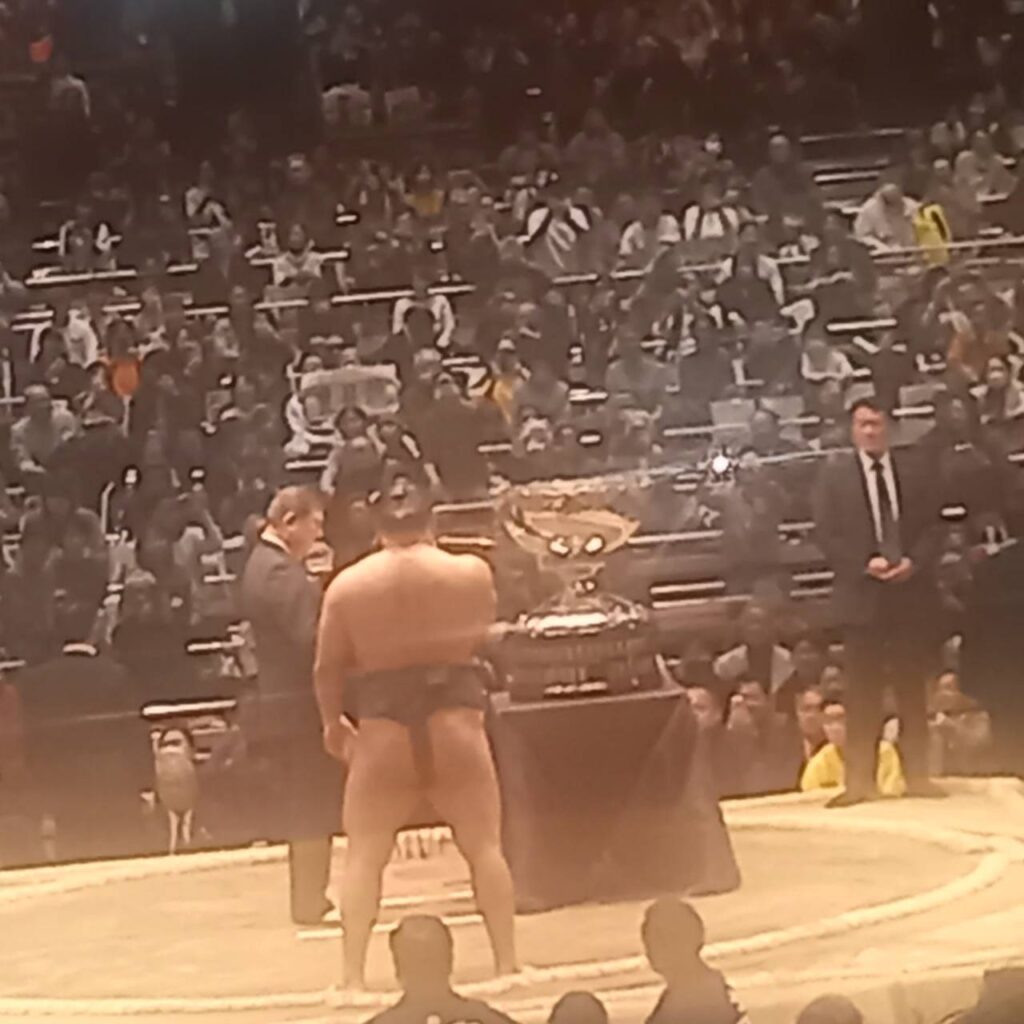山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2025年2月 トピックス】
これは実話だ。
◆職場に「礼仁」と書いて「レーニン」と名乗る後輩がいた。
親の憧れの人にあやかって付けた名であれば、穏やかではない。
「聖」と書いて「マリア」とルビが振ってあったのもあれば、また、「五月」と書いて「メイ」と名乗る方もいた。
いわゆるキラキラネームだ。
この程度はかわいいもので、いかがなものかという名前もある。
新智絵(にーちぇ)、七音(どれみ)、葉萌似(はーもにー)、美音楽(びおら)、希星(きらら)、姫星(きてぃ)。
詩と書いて「ぽえ」と呼ぶ方もおり、またゴルフの女子プロにも穴井詩(らら)もいる。
男も負けてはいない。
革命(れぼる)、未知(えっくす)、皇帝(しいざあ)、神(しはい)、なかには翔馬(ぺがさす)というのもある。
こうした「キラキラネーム」に対して、従来の●●男、●●郎、●●子はどう呼ばれているか。
「シワシワネーム」というそうだ。
失礼な話だ。
このキラキラネームは当て字が多く、画数が多いものが多く、親も子も不便だ。後悔して小学校に入る前に改名するという。
また、特に女性のキラキラネームは、お婆さんになっても使うといのはシンドイだろう。
一般的な呼び方ではないかと思うが、今どきの名前を聞くと、そうは言えなくなってきた感もある。
◆気の毒な名前
学校時代に「山本シュウ造(仮名)」というなかなかハンサムンな後輩がいた。
気の毒なことに、この「シュウ」にはとんでもない、「みにくい」漢字が使ってあった。
(悲しいかな・・・これは実話だ・・・)
親御さんも、よく、とんでもない字を使ったものだ。
かわいそうに。
いや、親御さんには他人には解らない、深い事情、深い意味があったのかもしれない。
(学23期kz)