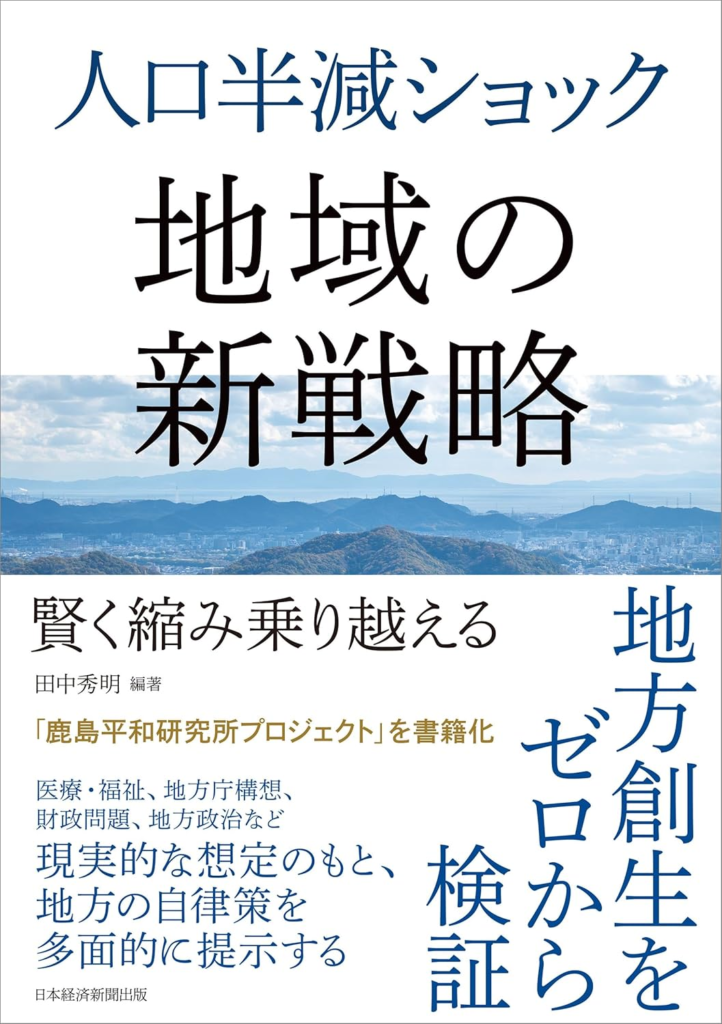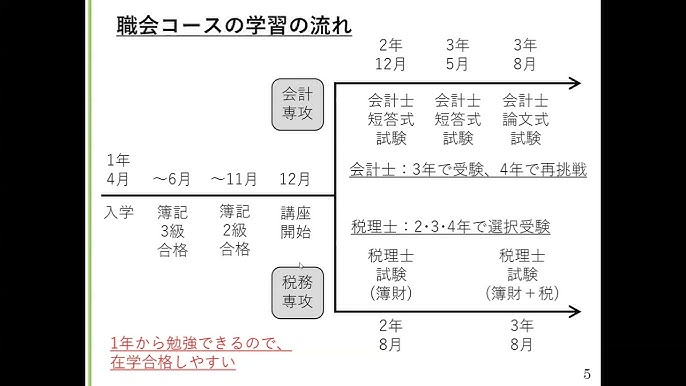山口大学経済学部同窓会
鳳陽会東京支部
【2025年12月 トピックス】
(学23期 K.O.)
◆年の瀬も押し迫り、来年の初詣は浅草の浅草寺へと考えている皆さんもおられよう。そこで、浅草寺本尊にまつわる話を一つ紹介したい。
浅草寺は「浅草の観音様」とも呼ばれるごとく、その本尊が観音菩薩像であることは一般にもよく知られているところであろう。ところが、この本尊は“絶対秘仏”として本堂宮殿奥深くの厨子に安置されており、浅草寺の貫首(かんじゅ)といえどもその姿を拝したことはない。
◆観音像の示現と絶対秘仏
寺伝(浅草寺縁起 14世紀)によると、628年に檜前浜成(ひのくまのはまなり)・竹成(たけなり)という漁師の兄弟が隅田川で網にかかった金色に輝く像を持ち帰って村長の土師中知(はじのなかとも)に見せると、村長はそれを聖なる観音像だと悟りお堂を創建し祀った、というのが浅草寺の始まりとされる。因みに、この三人は後に浅草神社の祭神として祀られ、毎年5月の三社祭の主役となる。
その後、この仏像は夢の中のお告げにより誰にも見せてはならない絶対秘仏としてお堂の奥深くに安置される。そして857年に比叡山から来山した慈覚大師円仁が秘仏の身代わりとして拝むための御前立(おまえだち)本尊を彫刻した。この観音像が毎年一度だけ12月13日の御宮殿開扉法要で開帳される御前立本尊とされる。
◆神仏混淆御改(おんあらため)の儀
時代は下って明治維新、それまで古来より神道と仏教を融合して信仰してきた「神仏習合」という宗教体制を改め国家神道を確立するため、明治元年に「神仏分離令」が発せられた。それに伴い、新政府から浅草寺に対して本尊が真に仏像であるかどうか実否を見分するとの達しがなされ、神祇官社寺役の10名ばかりが乗り込んでくるという事態となった。
浅草寺は「絶対」秘仏である本尊は開帳できないと強く抵抗を見せるが、“新政府の命はこれすなわち勅命である”として浅草寺を屈服させた。そして、明治2年6月14日、浅草寺側数名立会いのもと、役人が封印残らず切り解き、本尊を開帳した。
浅草寺の当時の記録では、この時僧侶たちは絶対秘仏の本尊を畏れ多く直拝できず、ただただ見分が終わるまで平伏していたという。一方の役人側は、当初居丈高にふるまっていたが、見分後は神妙な態度へと変わり「ご尊像は大切に護持なさい」と言葉を残し引き揚げたということである。したがって浅草寺側に本尊そのものに言及する記録は残っていない。また役所側にも公式記録は存在しないようだ。
◆後日談
昭和8年、一老婦人(見分に参加した役人の娘)が浅草寺の貫首を訪ねてきた。「父が秘仏改めの際に手早く半紙2枚に書き写したものを奉納したい」ということであった。像は素人のスケッチではあるが、木造のようで、両手両足を損じており、焼けた痕跡があったという。高さの記載はないが、俗説で言われていた一寸八分(約5.5センチ)というような寸法でないことは絵を通して想像できたという。その模写像は貫首と執事だけが拝見、桐箱に収め封印して本堂宮殿に奉安したという。
浅草寺本尊にまつわる話は以上のように伝承に始まり歴史に絡んで今日に至っている。本堂にてお賽銭をあげる際には、正面宮殿の扉の中の“御前立本尊”と、さらにその奥深く厨子に安置されているという本尊“聖観世音菩薩像”に少し思いを馳せてみてはどうだろう。
(学23期 K.O.)