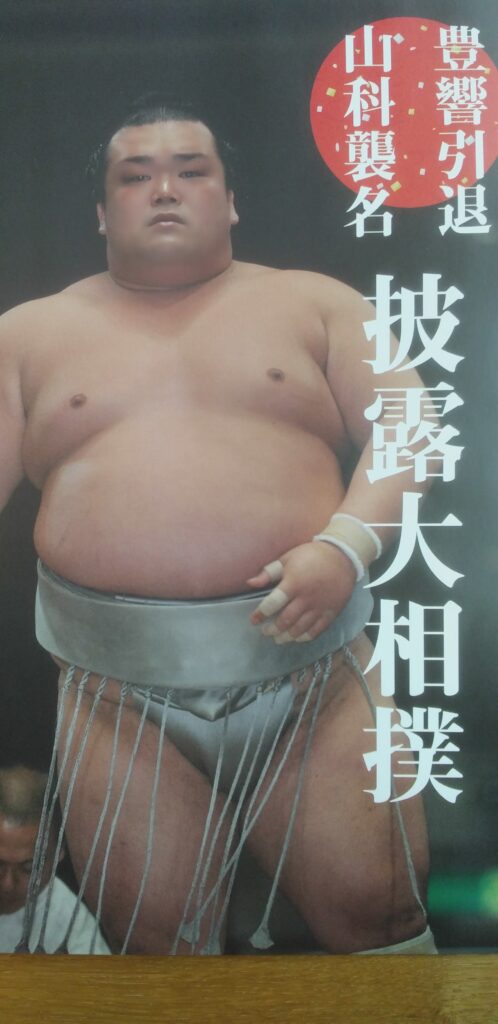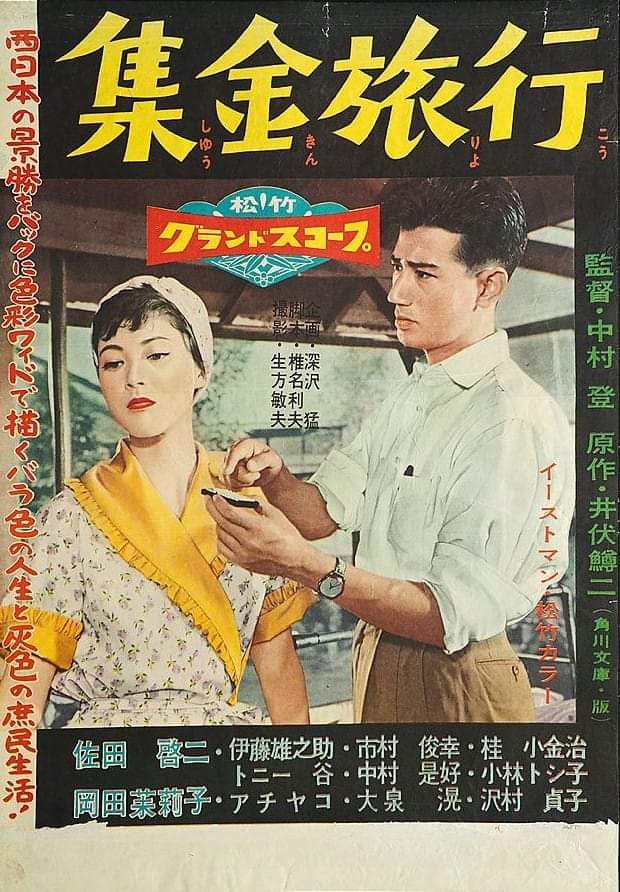【大学へのエール】
山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
【2023年2月トピックス】
国立大の授業料は安くない水準になっているが、大学の収入全体の中での位置づけをみると、授業料収入は支出の15%程度にとどまるという。今後日本の18歳人口は確実に減少していくのであり、授業料収入に期待はできない。
授業料以外、どのようにして収入が確保されているのか。
国からもらえるのが運営費交付金や補助金。これで賄えるのが全体の支出の約3分の2で、残りは寄付金などだという。
2004年の国立大学法人独法化に伴い、大学運営の自由度が増した代わりに、国からの運営費交付金が削減されることとなった。
収入の大どころは運営費交付金だ。しかしこれは毎年1%づつ削減されることになっており、大学としては、競争的資金や外部資金の導入に追われている。なぜ高等教育予算は窮屈になってきたのか。
それを乗り越える手立てはないのか。
◆文科省のライバル
予算は各分野、各事業、それを取り纏める各省庁が担当して予算が配分される。
全体のパイ(予算)は限られている。この中で予算を少しでも多く獲得しようと各省庁がしのぎを削る。
当然ながら、パイ、すなわち集まった税収を、どこに、どれだけ配分するかは緊急性、重要性を比較考量して決まる。
各省庁では、その必要性について業界団体を巻き込んで、膨大なデータを用い、分厚いペーパーを作成し、事業の必要性を訴え、予算要求してくる。
大学予算を含む文教予算は文部科学省が所管する。
想像しても文科省の競争相手は強敵が多い。
高齢化問題、雇用問題、コロナ対応を抱える厚生労働省。経済・中小企業、エネルギーを所管する経済産業省、地震・災害を担当する国土交通省、中国・北朝鮮問題を抱える防衛省、また欧米や中・露との外交問題を所管する外務省などなど。
どの役所も緊急的かつ重要な課題を抱えている。
こうした中にあって、彼らライバルを押さえ、文教予算を取ってくる必要があるのだが、これは至難の業だ。
文教予算の中には幼児教育、義務教育、中等教育もさることながら、ここで焦点を当てたいのは「大学」の高等教育予算だ。
大学向けの予算を引っ張ってくるには、世論、納税者を納得させるだけの効果をエビデンスをもって示す必要があり、予算の査定当局や重要閣僚、果ては総理に対して緊急性・重要性を認識させ、納得させる必要がある。
◆大学のパフォーマンス
しかるに日本の大学のパフォーマンスには疑問が投げかけられているのが実情だ。イギリスの教育関連情報誌「Times Higher Education」2023年でみた「大学の競争力」は、1位がオックスフォード大で96.4点。
他方、日本国内で敵なしの感がある東大は75.9の39位。
世界のトップ100校で日本の大学の名が出てくるのは68.0点の京大のみ。しかも両校とも昨年よりランクを落としている。
数年前は東大もランクが多少は上に位置し、100位以内に日本の大学は数校が入っていた記憶があるが、ランクダウンが続いており、いまだに歯止めがかかっていないのは情けない限りだ。
◆学生の就職先
また、大学の就職先の話でも、ショッキングな話がある。
最近の学生は4年制の大学を出ても、実際の職場には短大や高卒程度の職に就いている者も多いというのだ。
こうした中で、文部予算、中でも高等教育予算を拡大させることは関係者や一般納税者の理解を得るのは難しい。
◆正々堂々と正面突破
世論や納税者を納得させるにはデータを示すことだ。これまでデータ化や計量化しにくかった分野でも工夫してデータで示すことが重要だ。調査や研究も差別化し、独創性・専門性を高めることが必要であることは言うまでもない。
これまで大学改革が叫ばれてきたが、改革が進展しなかったのには大学改革に対する評価の在り方の問題も挙げられている。
一般的に、学内、あるいは大学関係者などいわゆる身内だけの甘い評価制度が問題になっているとの話はよく聞かれる。
また情報の開示も渋るべきではない。
むしろ、情報を積極的に開示し、データ化し、また教育の成果を上げて成果を示し、正面から正々堂々と予算を取りに行くような取り組みをすべきだ。しかも中長期的に取り組んでいかないと効果は出ない。
◆教育はみんなで
大学では調査や研究も大事だが、これは車輪の片方。もう一方は教育だ。
学生に良い教育を施すには、熱く指導できる教員の方々存在が要る。
しかしこの要件は必要条件であるが、十分条件ではない。
教員だけではなくより多くの関係者を引っ張りこむのも一考だ。
学生の教育を大学の先生たちだけのものにとどめてはいけない。大学改革に向かう学長、学長を補佐するスタッフ職員、大学職員の方々はもちろんのこと、学生の親、地元企業、地元自治体、それに加え卒業生も一体となって学生教育を支えるべきではないか。
鳳陽会の卒業生もこれまでも、世界で、また日本の中枢で活躍した社会経験豊富な同窓生があまたいる。場合によっては、各業界で人材採用の担当者になっている卒業生もいるはずだ。
学問を学び、世に出ていく学生に対して、時には相談に乗り、ある時はヒントやアドバイスを与えることで何がしか貢献できるのではないかと思う。
大学教育は、より開かれたものであってほしい。
・・・続く
(学23期kz)
山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
★SNSに登録していただき、フォローをお願い致します。