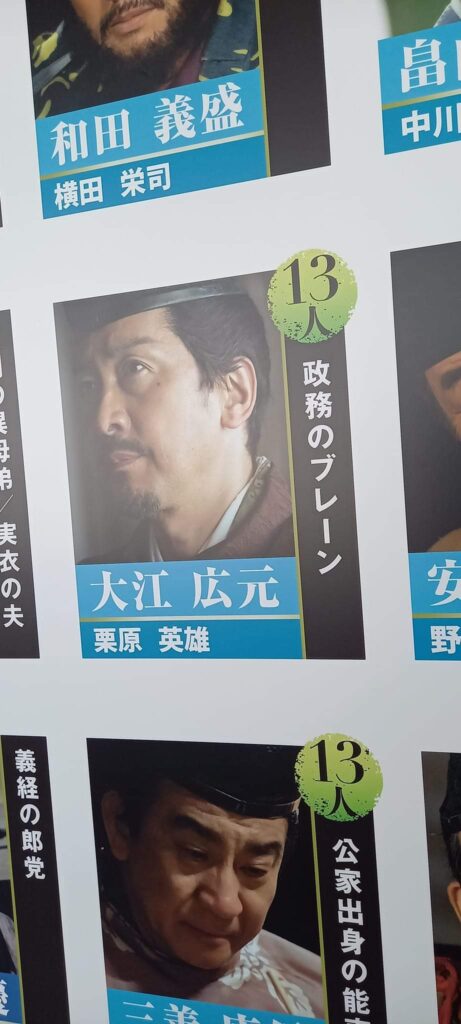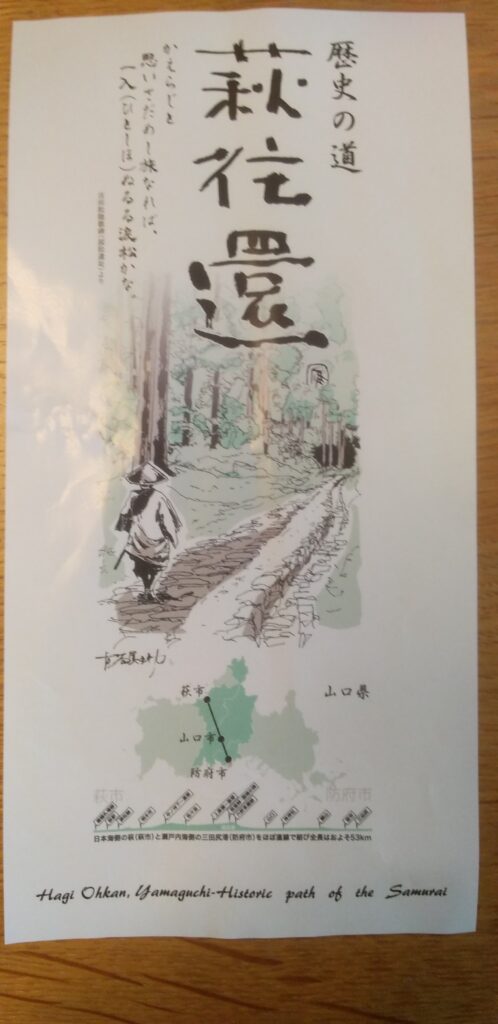山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
【12月トピックス】
投資をしない日本企業、大きな視点を欠いた経営
国会で取り上げられる企業の内部留保の問題。利益剰余金のことだ。2020年度末の内部留保は2012年度以降9年連続で積み上がり484兆円と、国のGDP540兆円の約9割に達する。
なぜ投資をしないのか。
バブル崩壊、リーマンショック、コロナで事業環境が変化し、手元資金を潤沢に持っておかないと経営に支障が出ると考えるようになったことが大きく影を落としているのではないか。
投資をするには、アニマルスピリットのほか、事業環境の変化を察知しながら、先を見据えて行動し、勝てる展望を持つことが必要となる。
これが持てないのだ。
◆人に対する投資
日本企業は終身雇用、人を大事にするということが建前であり、日本企業の特徴とされてきた。しかし、リーマンショック後は決算上債務超過になることを恐れ、人材を不要資産よろしく社員のリストラが横行した。
人に対して投資をし、この先企業を支える人を育てる姿とは真反対の姿だ。
ここにも日本企業は長期的視点を失い、短期的な決算重視の短期的経営になったようだ。
◆短期的経営か
短期的経営で業績が伸びていけばよいが、必ずしもその保証はないし、そうなってもいない。
すなわち短期的経営ともいえないのではないか。
短期的経営とは、目標があり、短期的な判断をつなげて業績を上げるということだが、大きな方向があればの話だ。
大きな経営方針がない場合、どうするか。
言っておくがシェアを伸ばす、シェアが伸びるのはあくまでも結果。
ここに目標を置いてはならない。利益を度外視した激烈なシェア競争の下で犠牲が増える。
◆長期的視点が目立つ世界の企業
むしろ欧米企業の方が長期的視点に立って考え、行動している。
人権問題への取り組み、環境問題、ステイクホルダー重視の姿勢になっている。
日本はその後追いをしているようにみえる。
いつの間にか、日本と外国企業で経営姿勢の長短逆転が生じている。
短期的経営で堅実に業績を伸ばし、日本経済の成長に貢献しているのであれば問題ないが、日本経済は世界に置いて行かれており、世界の背中が年々小さくなっている感がある。
これではいけない。
(学23期kz)
山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
★SNSに登録していただき、フォローをお願い致します。