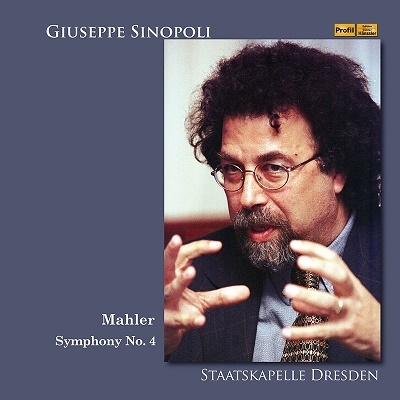山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
【2023年4月トピックス】
◆同期会の話題
総会に参加すると、まず同期同士が集まることになり、立ち話で近況を報告し合う。
やはり、同期が一番親しみやすく、話しやすい。
同期の間では、現役時代は仕事上の勇ましい話が多かったが、現役を退くと学生時代の懐かしい話や海外を始めとする遠出の旅行の話が出始めた。しかし最近では健康のことが話題にのぼることが多い。
どういう病状が出て、どのような手術を、どこで受け、費用はいくらかかったか。
同じような問題を抱える者にとっては大事な情報交換の場となる。
◆参加者名簿
総会には出席者名簿が配られる。
名簿は期別順に表示され、出身高校や出身ゼミも付記されている。
これが同窓のつながりを深める契機となることもある。
総会の後の懇親会の場で、私は名簿をもとに高校の同窓、あるいは同郷の先輩・後輩のところへ、またゼミの先輩・後輩のところへ挨拶しに行くようにしている。
一人の先輩と面識ができれば、先輩は同期の方を紹介してくれる。これがありがたい。
一人の後輩と面識ができれば、近々に一杯飲もうと持ち掛ける。何といっても後輩は愛すべき存在だ。
◆鳳陽会東京支部の県人会
九州にある私の同郷の同窓生の数は、おひざ元の山口県や同じ九州ながら山口の隣県である福岡県に比べて限られている。
それだけに参加者名簿を見た瞬間、同郷の高校名が付された先輩・後輩は自ずと目に飛び込んでくる。
昨年の総会の参加者名簿がきっかけで、同郷の先輩・後輩の皆さんと県人会を開催するようになった。
会場は神保町の中華料理屋と決めている。
1~2年違いの先輩や後輩ではなく、年が相当離れた同郷の先輩や後輩たちから話を伺う。
こうした場は得難いものだ。
当時の山口での生活、就職活動の話、現役時代の武勇伝。近況。
みなさん一人一人が順番で話すたびに、小宇宙が会場に広がる。
面白い。
止まらない。
終わらない。
この県人会、来るゴールデンウィークに第3回目の会合を開く。
(学23期kz)
山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部