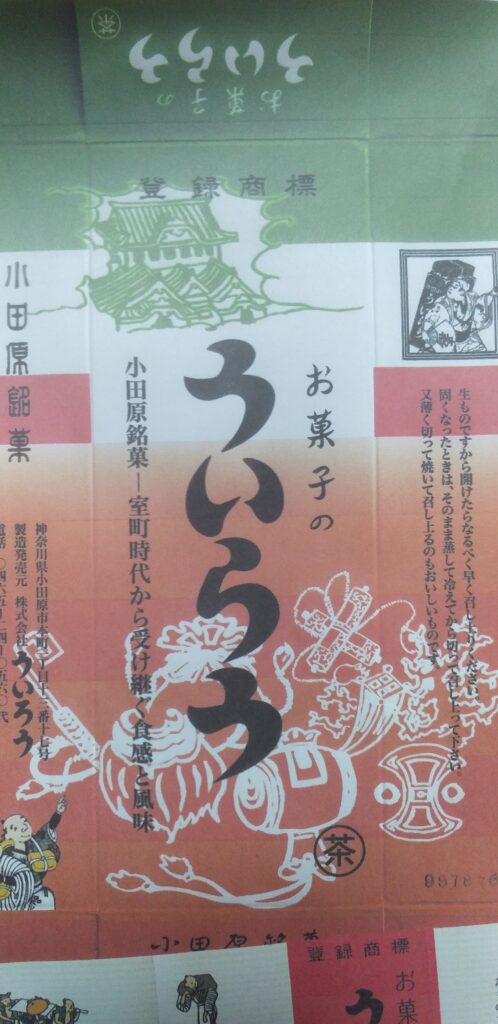山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
【2023年3月トピックス】
ようやく春が巡ってきた。
それでも北風が冷たく、厳しい朝を迎える日もある。
いつぞや真冬にやったゴルフを思い出した。
◆冬場の朝一番
北関東では、ティーが地面に刺さらないほど地面が凍っている場合が多い。
白い息を吐きながらティーグラウンドに立つと、凍てついたティーグラウンドにティーを刺す穴あけ器(ティー・ボーリング)が置いてある。
右手で鉄の取っ手を持ち上げ、凍った地面に振り下ろすのだが、取っ手も凍っており右手に痺れが残る。
右手に手袋が欲しいところだが、グローブをしているのは左手。何ともチグハグ。
左手で穴を開けようにも今一つ力が入らない。
やはり頼りになるのは利き手の右手だ。
◆真冬特有のゴルフ
真冬のプレーでは面白いことが起きる。
池に打ち込んでもボールは氷の上を跳ね、グリーンに出てくる。
「こいつはいいや!」
結構、トクをした気分になる。
しかし、そのあとに落とし穴が待っている。
グリーン近くから寄せに入るが、凍ったグリーンの上ではボールが止まってくれないのだ。
とてもスコアにならない。
鏡の上とは、まさにこのこと。
凍ったグリーンで特に困ったのは、かなりの段差があるパー3の打ち下ろしのホール。
グリーンを捉えたと思った打球はマジックボールのように2~3度強く飛び跳ね、大きな弧を描きながらグリーン脇の林へ消えた。
次のプレーヤーも同様。
一緒に廻ったパートナーの打球も全てロストボールになってしまった。
凍ったグリーン、恐るべし。
プレーヤーの予想や願望を、ことごとく打ち砕く。
◆止せばいいのに
凍てつく真冬にはゴルフを止めておけばいいのに、そうはいかない。
ひと月もふた月も前から、仲間と楽しみにしていたゴルフ。
仕事に段取りをつけ、家族を納得させ、プレー代の捻出にメドを付けて、仲間とのプレーを楽しむことに専念する。
そしてプレー後には特別の楽しみが待っている。
乾杯だ。
若い時は、雨が降ろうが、雪が降ろうがゴルフを決行!
仲間との無謀な初志貫徹の契り。
ああ、今となっては懐かしい。
(学23期kz)

穴あけ器(ティ・ボーリング)
山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部
★SNSに登録していただき、フォローをお願い致します。